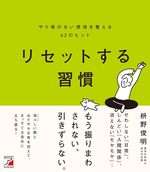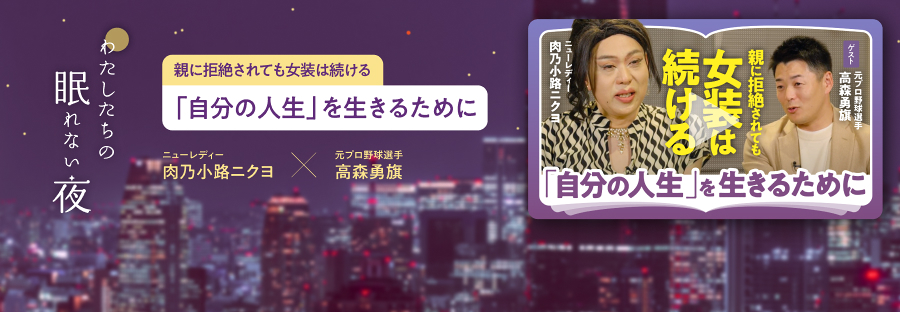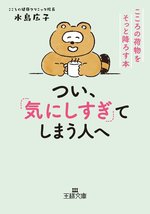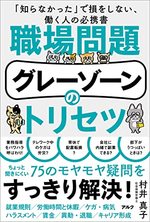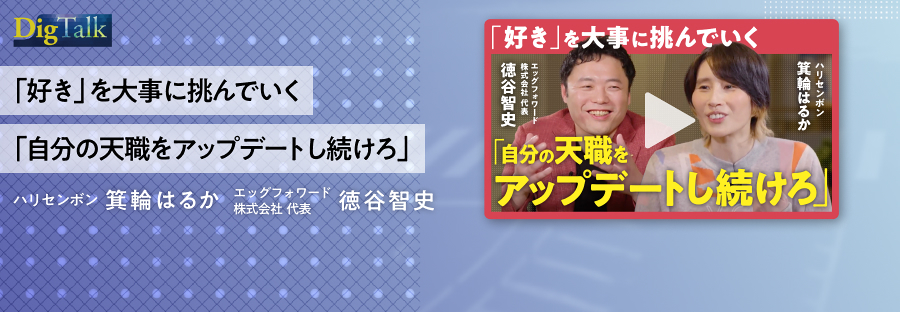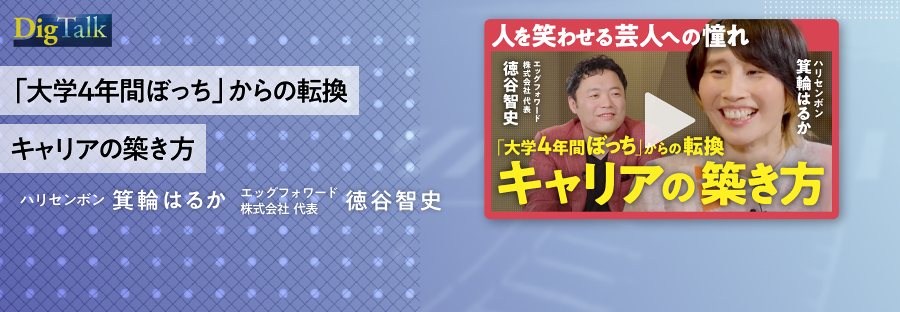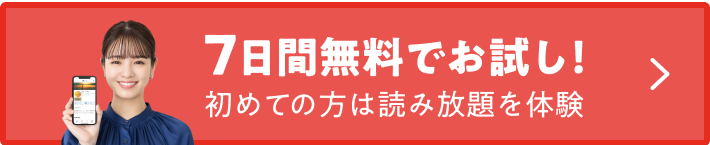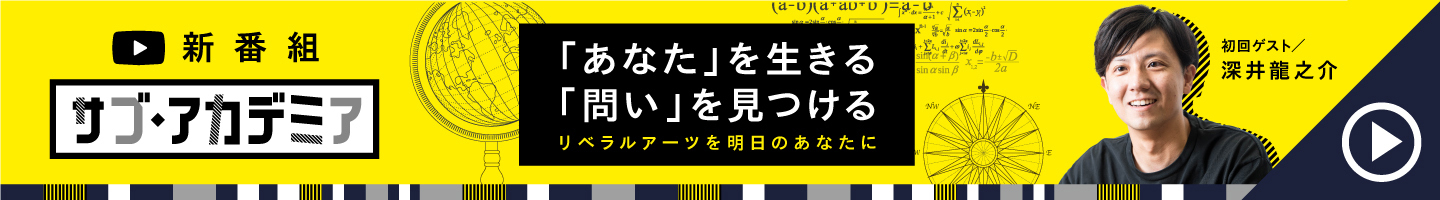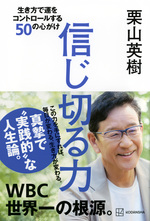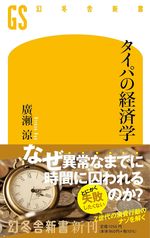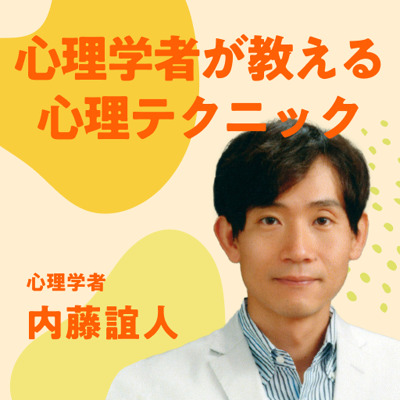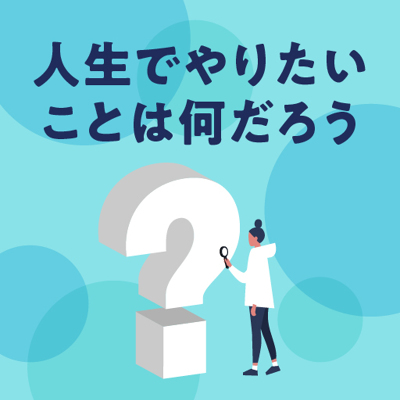最新の要約

ユーザーファースト 穐田誉輝とくふうカンパニー
野地秩嘉
柳井正氏は、良質なカジュアルウェアを安価で提供すべく、ユニクロブランドを築いた。
孫正義氏は、情報革命によって人々がよ...
/summary/3790
プレイリスト
flierチャンネル
イチオシの本
インタビュー
スペシャルコラム
お知らせ
2024.02.15
2/15(木)放送の日本テレビ「ZIP!」でflierが紹介されました!
2024.02.13
2024.02.13
2/13(火)放送のTBS「ひるおび」でflierが紹介されました!