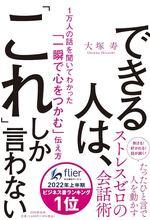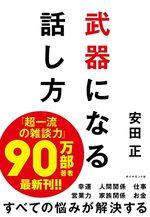だれにでもあるバカの壁
バカの壁とは
「話してもわからない」ということを著者が痛感した例がある。ある夫婦の妊娠から出産までを追ったドキュメンタリーを薬学部の学生に見せたときのことだ。勉強になったとの意見が多かった女子学生に対し、男子学生は「保健の授業で習ったようなことだ」という感想を抱いたのだ。男子学生は女子学生ほど出産に対して、積極的な発見をしようという姿勢を見せなかったといえる。
このことは、「自分が知りたくないことについては自主的に情報を遮断してしまっている」ことを示している。「知っている」ということの実態はその程度であり、ここに存在する壁が、一種の「バカの壁」だ。
同じ事柄を見聞きしても、現実の捉え方は三人いれば三者三様になる。しかし現代では、「自分たちが物を知らない、ということを疑う人」がどんどん減っている。一定の情報を得てもわからないことはたくさんあるのだ。現実のディテールが「わかる」のは、そう簡単ではない。
「客観的正しさ」を安易に信じる姿勢は、非常に怖いものだ。「科学の世界なら絶対があるはずだ」と信じる人は多いかもしれないが、そんなことはまったくない。たとえば「地球温暖化の原因は炭酸ガスの増加だ」ということがあたかも「科学的事実」のように言われているが、これは一つの推論に過ぎない。そうして事実と推論を混同している人が多いのだ。科学を絶対的なものと妄信すると危ない結果を招いてしまうかもしれない。
入力は同じでも出力は人によって変わる

「知りたくないことに耳をかさない人間に話が通じない」ことは、よくあることだ。このことは、脳の入出力の面から説明できる。入力される五感をx、出力としての人間の反応をyとすると、y=axという一次方程式のモデルが考えられる。ここでのaという係数は、いわば「現実の重み」だ。
通常、入力に対して何らかの反応があるのでaはゼロではないが、非常に特殊なケースとしてa=ゼロ、つまり入力があっても全く行動に影響しないケースもある。入力がその人にとって現実的ではないということを指す。たとえば足元に虫が這っていても気にせず無視するケースだ。興味がなければ完全に目に入らなくなる。
逆に、a=無限大となるケースの代表例は原理主義だ。ある情報や信条が、その人にとって絶対的な現実になる。その人のすべてを支配する。
aは、感情を考慮に入れれば、ゼロより大きくも小さくもなる。行動にはプラスマイナスがあるのだ。aがあるから行動が相当に変わる。
aの値によって、「ある状況において、その人が適しているか、適していないか」も決まってくる。「基本的に世の中で求められている人間の社会性」とは、「できるだけ多くの刺激に対して適切なaの係数を持っていること」だろう。
共通了解と個性

「わかる」ことには「共通了解」と「強制了解」の2種類がある。
「共通了解」は「世間の誰もがわかるための共通の手段」のことで、言語はここに分類される。その言語からより共通の了解項目を抜き出してくると、「論理」や「論理哲学」、「数学」になる。数学は、証明によって強制的に「これが正しい」と認めさせられる論理であるため、「強制了解」という領域になる。
人間の脳は、「できるだけ多くの人に共通の了解項目を広げていく方向性」をもって進化してきた。共通了解は「多くの人とわかり合えるための手段」であり、共通の情報を広げるマスメディアが発展していくことは自然な流れだ。
一方で、「個性」や「独創性」を重宝する動きが増えてきた。共通了解を広げることで文明が発展してきたことを考えると、「個性」が大切だというのは明らかに矛盾している。実際には、個性が大事だとしながら他人の顔色を窺っている。その現状をまずは認めなくてはならない。
会社のような組織に入れば徹底的に共通了解を求められるのに、「個性を発揮しろ」と要求される。その結果、「マニュアル人間」が生まれた。