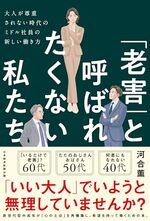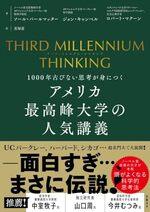お金を払ってでも笑いたい
「笑い」はHappy Pills
中野氏はまず、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2023」のメインプログラムのひとつである「Happy Pills」という展示を紹介する。これは写真家のパオロ・ウッズとジャーナリストのアルノー・ロベールが世界各地を回り、現代人がいかに薬を使っているかを調べた成果である。
中野氏が特に印象的に感じたのが、「世界幸福度ランキング」の上位と「抗うつ剤の最多消費国」ランキングの相関をとった表だ。これを見ると、人々が幸せに暮らしている国では、同時に抗うつ剤が大量に消費されていることがわかる。その意味を考えるとぞっとすると中野氏は語る。
そういう薬を服用しないと人は幸せになれないというわけではない。人の脳内ホルモンにあるベータエンドルフィンというホルモンは、幸福感をもたらすと同時に、モルヒネの数倍強いといわれる鎮静作用を持っている。この分泌を促す仕組みのひとつに、「笑い」がある。笑うと幸せを感じられ、痛みが軽くなり、気持ちが楽になる。それを経験的に知っているからこそ、人は昔からお金を払ってでも「笑い」の場を求めてきたのだろう。「笑い」は過酷な現実を生き延びるための「Happy Pills」たりうる。
笑いを読み解く能力がある

お笑いは、人間社会のしんどい部分を拾ってネタにする方がやりやすいのか。中野氏がそう問いかけると、兼近氏はそれを肯定しつつも、観客サイドの情報を読み解く力、リテラシーが高くなければ笑えないという側面があると語り出す。