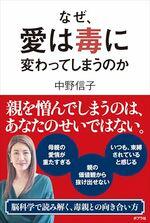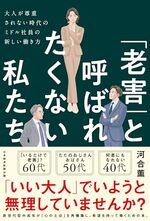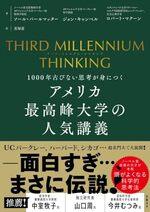【必読ポイント!】 子どもの壁
子どもを上手に放っておきたい
少子化が大きな問題になっている。少子化が進めば国全体に大きな影響があるのは言うまでもないが、出生数よりも心配なのは子どもの自殺の多さだ。2023年の日本人の10〜30代の死因のトップは「自殺」。若い世代の死因で病気が少ないのは当然ではあるが、他国と比べて事故より自殺が非常に多いのが特徴だ。
若い世代にここまで自殺が多い社会は健全とはいえない。若くして健康の問題を抱えている人もいるが、基本的には活力にあふれ、人生で一番楽しい思いをしていなければならない時期であるはずなのに、死にたくなるような思いをしている子どもが多いということなのだから。虐待などの明らかな問題がない家庭であっても、子どもにとって本当に良い環境をつくれているかを本気で考え直さなければならない。
いまの子どもたちは習い事が多くて忙しいとよく聞く。親は手間やお金をかけて子どもを大切にしていると思っているかもしれないが、あれこれ習わせれば子どもが良い方向に育つというのは幻想ではないだろうか。乱暴に言ってしまえば、子育てにあたって親が気を使うべきは、子どもを危ない目に遭わせないことと、食事をちゃんと与えることくらいである。
子どもに手をかけたほうがいいという錯覚

著者の世代は、親に手をかけて育てられたことのない人がほとんどだ。こう言うと、「時代が違う」と思われるかもしれないが、時代が変わっても変わらないことは多くある。
水泳やピアノのように、習わないと身につかないことを習う意味はたしかにある。だが、それらの英才教育をしたからといって、みながプロフェッショナルになるわけではないことはわかりきったことだ。
小泉英明さん(日立製作所名誉フェロー)は、長年子どもを対象にした「コホート研究」に取り組んでいる。コホート研究では、同じ人を長期間追跡して調査し、何らかの要因と結果を検討することができる。一人だけの変化を見ても意味がなく、統計的に意味のあるデータを取るには数千人を対象に長期間調査をしなければならない。手間も予算もかかる研究だ。
小泉さんによれば、1、2歳くらいまでに褒めて育てた子どもとそうでない子どもでは、その後の社会での能力に差が出たそうだ。乳幼児期には、褒めて育てられるのが非常に大切だということだ。








![[新書版]生きる意味](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F4116_cover_150.jpg&w=3840&q=75)