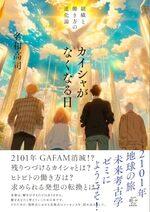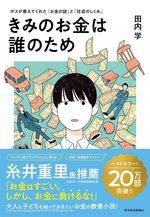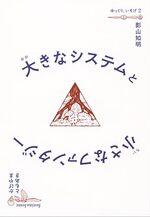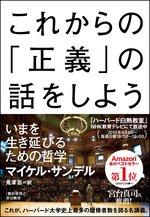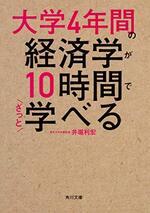金融緩和の是非
中央銀行が主役なのは錯覚だった
第二次大戦後、西洋諸国における経済政策モデルを築いたのは、経済学者であるケインズの後継者たちである。彼らが景気対策で重視したのは、中央銀行の行う金融政策ではなく、政府自体が裁量する財政政策の役割であった。これは、1930年代の世界大不況の際に、金融を緩和して金利を引き下げすぎた結果、金利がゼロになってしまい、それ以上の金融緩和が意味をなさなくなる状況に行きついたという経験があるためである。ケインジアンたちは、そのような状況を「流動性の罠」と呼び、その罠にかからないようにするための財政政策が必要不可欠だと主張した。
しかし、そうした財政政策重視の経済政策運営はやがて行き詰まりを見せる。ケインジアン的な政策運営を行っていた米国で、不況とインフレーションが同時に発生する「スタグフレーション」が起きてしまったことは、その象徴的な出来事である。こうして、大戦後の経済政策の主役であった財政政策はその座から降ろされ、再び金融政策が脚光を浴びはじめた。
フィリップス曲線の「発見」も、この流れを後押しした。フィリップス曲線とは、賃金上昇率と失業率との負の相関に関する経験的な事実を表したものだが、この賃金上昇率を「インフレ率」に読み替え、失業率を「景気」と読み替えると、「高めのインフレ率を許容した方が景気は良くなる」とも解釈できる。そのため、金融政策をつかさどる中央銀行こそが、物価と雇用を調整するカギを握っているという雰囲気が次第に生まれていった。
だが、それは錯覚にすぎなかった。中央銀行は結局のところ、「流動性の罠」の問題からは解放されていなかったのである。そのことを最初に明らかにしたのが、1990年代半ばの日本であった。
「流動性の罠」が帰ってきた!
当時、日本はバブル経済後の急速な景気の落ち込みに悩まされていた。この手詰まりの状況を「流動性の罠」の再来と指摘したのが、経済学者であるポール・クルーグマンである。クルーグマンは、「流動性の罠」から脱出するための方策として、日銀が金融政策運営において許容するインフレ率について、より長期的な視野から柔軟な態度を取るべきだと主張した。「流動性の罠」はそもそも、名目金利の世界で起こっている問題なのだから、世の中のインフレ期待が上振れすれば、自然と解決されるというわけである。
実際、日銀がその後にとった「時間軸政策」は、クルーグマンの提案に近いものであった。これは、将来から豊かさを借りてくることで、インフレ期待を高めようとする政策だったといえる。しかし、そもそも未来は豊かになると人々が信じていなければ、大きな成果など期待できるはずもない。いくらやり方を工夫したところで、日本が経験したようなデフレの場合、金融政策では限界があるわけだ。
しかし、金融緩和策が効かないのは日銀の姿勢が中途半端なためであり、もっと数字を大きく掲げて世間に訴えれば、インフレ期待を起こすことができると考える人も少なくなかった。2013年に打ち出された「異次元緩和」は、そうした背景のもと支持され、実行された金融政策だ。ほとんどゼロである金利のわずかな動きを追いながら政策を実行するのではなく、日銀の貨幣供給量を金融政策の中核に据えることで、「流動性の罠」のような面倒な議論を迂回し、金融緩和を進める中央銀行の決意の固さをアピールできるというわけである。
第3の選択肢の登場
「異次元緩和」が実行されたことにより、たしかに人々の心理は大きく変わったし、株式市場にも活気が戻ってきている。だが、肝心の物価目標はまったく達成できていないのも事実だ。