KPIの基礎知識
KPIとは何か?

KPIとは「Key Performance Indicator」の略であり、「事業成功の鍵(Key Performance)」を「数値目標(Indicator)」で表したものである。つまり、この「事業成功」が何なのかを理解していることが、KPIマネジメントの起点となる。
まずは、KPIマネジメントにおける主要登場人物を紹介する。1つ目はKGI(Key Goal Indicator)。期末に到達したい最も重要な数値目標、いわば「最終的な目標数値」を指す。企業全体ならば利益目標が、営業組織ならば売上目標数値が、事業開発ならばユーザー目標数などが、それにあたる。このゴールの中身と数値について、ステークホルダー間で認識がずれないように、事前の確認が必要だ。
KGIについて合意を得られたら、次に確認すべきは2つ目の主要登場人物、CSF(Critical Success Factor)だ。これはKGI達成のためにやるべきプロセスのうち、「最も重要なプロセス」であり、事業成功のポイントといってもいい。たとえば、営業組織ならば、ゴールとなる売上を上げるために行う顧客訪問や提案活動などのプロセスを指す。大事なのは、このCSFが現場でコントロールできるプロセスでなければいけないという点だ。
いよいよ3つ目がKPIである。CSFをどの程度実施すれば、期末にKGIが達成できるのかを示す数値といえる。要は、KPIはKGIの先行指標であり、CSFの数値目標である。KPIを達成すると、KGIも達成できるという関係性だ。
KPIマネジメントとは、このKGI、CSF、KPIの3点をステークホルダー全員で共有・実行・改善し続けることである。
ダメダメKPIの作り方でありがちなこと
組織でKPIマネジメントを導入したものの、設定が間違っているせいで、うまくいかずに挫折してしまう例が後を絶たない。KPI設定でありがちな間違いを挙げてみよう。1つ目は、たくさんの数値目標を設定しているケースだ。これでは単なる数値マネジメントにすぎない。
2つ目は、現場でコントロールできない指標をKPIとして掲げているケースである。たとえば、GDPや有効求人倍率をKPIに設定しても、その数値改善に対し、民間企業に打てる手はない。
3つ目は、先行指標ではなく遅行指標を選んでいるケースである。KPIの設定で重要なのは、できるだけ旬で、可能ならリアルタイムで把握できる数値を選ぶことだ。
4つ目は、定期的にモニタリングする指標のなかに、CSF候補がないケースだ。そもそも誤った指標や数値を見て管理していては、事業運営がうまくいくはずがない。まるで、スピードメーターが間違った自動車で運転しているようなものだ。
【必読ポイント!】 KPIマネジメントの正しいステップ
KGIと現状とのギャップを確認し、プロセスをモデル化する

ではどうやってイケてるKPIを設定し、運用、改善していけばいいのか。正しいKPIマネジメントのステップを順に紹介する。
ステップ1は組織の目的地となる「KGIの確認」、ステップ2は「現状とのギャップの確認」である。現状の延長で行くと期末にはどうなるかを予測し、KGIとのギャップを把握するのだ。
ステップ3は「プロセスの確認・モデル化」である。自社のビジネスを数式にしてモデル化するのだ。営業活動で、「このままでは利益目標が達成できない」という状況を例にとろう。利益を上げるには、売上を上げるか、費用を削減するしかない。前者の場合、売上は「アプローチ量×歩留まり率(コンバージョンレート)×価格(平均単価)」という掛け算の数式で表せる。売上アップの選択肢として考えられるのは、「アプローチ量を増やす」「歩留まり率を向上させる」「価格を上昇させる」の3つだ。
CSFを絞り込み、KPIを設定する
次は、これらの変数の中で、最も重要なプロセスを絞り込むことになる。これがステップ4「CSFの設定」だ。まずは、先述した数式に登場した要素を、定数と変数とに分ける。変化が実質少ないものや、自分たちでコントロールがきかないものは定数と扱えばよい。
事業開発担当だった著者は、「アプローチ量×歩留まり率×価格」の各要素の中で、コントロールがきかない価格を定数としていた。すると残りはアプローチ量と歩留まり率。この変数からCSFを選択する。

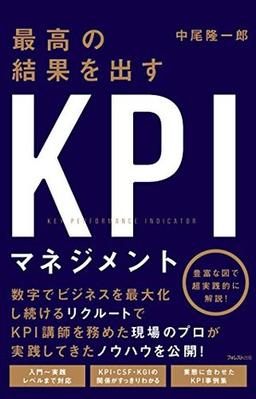















![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)


