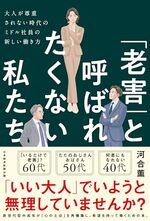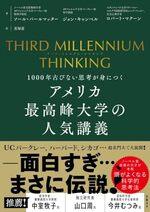【必読ポイント!】心をつかむ技術
弱者に寄り添う

独裁者は、必ずしも弱者の敵だというわけではない。多くの独裁者が“弱者救済”のための政策に取り組んでいる。
アドルフ・ヒトラーが政権を握ったとき、ドイツの失業率は40%に達していた。しかしヒトラーが抜本的な対策を講じた結果、わずか4年でほぼ完全雇用を達成することとなる。ドイツはそのころ、第一次世界大戦に敗北し、多額の賠償金を払わざるをえなかった。そんな状況下、ドイツ国民はますます熱狂的にヒトラーを支持するようになっていったのだ。
日本の独裁者、織田信長にもまた、弱者に寄り添う心があった。彼は比叡山の焼き討ちや長島一向一揆での火攻めなど、激しい宗教弾圧を行った人物である。しかし信長は、物乞いをする身体障害者を不憫に思い、町の人たちに彼の世話をするよう頼んだこともあった。木綿20反を渡したうえで、それを売った費用の半額を使って助けてやってほしいという具合に指示を出したという。
これらは、弱者に寄り添うことで頼りがいを演出し、信頼を獲得するという独裁者たちの戦略のひとつだ。
ワンフレーズを繰り返す
民衆は理解力に乏しく、忘れっぽい。だから独裁者たちは、印象的なワンフレーズをしつこいほど繰り返すという手法を採る。
独裁者ではないが、日本でもこの手法を使った政治家がいる。小泉純一郎だ。彼は「私が自民党をぶっ壊す!」と強いメッセージを発信していた。バラク・オバマが繰り返した「Yes We Can」にも同様のねらいがあったのだろう。
ヒトラーが使ったのは「すべての労働者に職とパンを!」というフレーズだ。彼は大衆の理解力を全く信用していなかった。小難しく述べるよりも、わかりやすいフレーズをひたすら繰り返すことが重要だと冷酷に分析していたのだ。
老若男女に思いを伝え、彼ら彼女らから支持されるためには、要点を絞り、短くわかりやすいフレーズを何度も繰り返す必要があるといえよう。
ワンフレーズの力は、マネジメントにおいても注目を集めている。