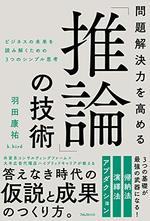【必読ポイント!】 「哲学的な問い」の思考法
考え抜く力を養うためのレッスン
この本は、ある物事や事象に対し、まず「直感」をもとに立場を決め、それを正当化しうる「理屈」を組み立てる方法を伝えるために書かれた。いわば、「考え抜く力」を養うためのレッスンである。
考えることは面倒な場合が多いだろう。しかし、苦しいことや悲しいことも当たり前に起こるのが人生である。それに立ち向かい、自分なりの答えを出すときに味方になってくれるのが、「考え抜く力」である。本書では、読者が社会の常識や理不尽に流されることなく、自分の頭で物事を考え抜けるようになるための方法論を、「8つの思考実験」を通して提供する。
「いかに知らないか」を明らかにする

では、具体的にどのようなことを考えていくのか。たとえば、「ウソをついてはいけない」と大人たちはいう。しかし、ウソをつくことは、果たしてどんな場合でも「いけないこと」だろうか。
哲学者のカントは次のような問いをたてたことで有名だ。「友人を殺人者から守るためのウソは許されるのか」。これを大人にたずねたら、ほとんどの人が「この場合はウソをついてもいい」と答えるだろう。「ウソも方便」ということわざがあるように、友人を守るためならウソをついてもいいと考えるにちがいない。
こうしたとき、大人たちの「矛盾」に気づき、問い直さなければならない。「ウソをついてはいけない」という常識自体、そもそも妥当ではないのではないかと。理屈をきちんと説明できないのに、ただやみくもに押し付けられているルールや常識が、世の中にあふれていることを知るべきだ。直感的に「なぜ?」と思ったとき、「それが正しいのか」と問い直してみると、その根拠は必ずしも明確でないことが多い。いかに多くの大人が、疑いをもつことなく、あいまいな常識を強制してきたのかがわかるだろう。
古代ギリシアの哲学者、ソクラテスは、社会の中で常識とされている知識が「ほんとうに正しいのか」を確かめたいと考えた。というのも、彼にはその知識が「どうして正しいのか」がよくわからなかったからだ。そこで、知識人とされている有力者たちに聞いてまわった。だが、有力者たちが、その知識を裏付ける根拠をいかに知らないかが暴露されることとなった。ソクラテスは、私たちが「いかに知らないか」を明らかにすることから哲学をはじめたのである。これがかの有名な「無知の知」である。
考え抜くための4つのステップ
ソクラテスの「哲学的な問い」は、小さな子どもが大人に発する「素朴な疑問」と似ているように見える。だが、哲学者は常識を知らないから聞いているのではない。常識を知ったうえで、あえてその根拠を問い直しているのである。
「哲学」とは、常識がすでに出来上がっていることを前提に、それをあえて解体しようとする試みだ。問い直すべき常識を知らなければ、そもそも哲学などできない。常識を身につけてもなお問い直すことができるのが、「哲学者の条件」だ。
私たちは常識に対して窮屈さを感じることがある。著者はその直感的なモヤモヤを大切にしてほしいと説いている。なぜその違和感が生じたのかを徹底的に検証してみるのだ。そのために必要な「考え抜く力」を伝えるのが、本書の狙いである。
「考え抜く」ためには4つのステップがある。これは、直感を理論武装するための思考法でもある。
ステップ1:直感をもとに立場を決め、その根拠を表明する。
ステップ2:根拠に説得力を持たせ、それがどれだけ妥当なものであるかを検証する。
ステップ3:別の観点から問い直す。
ステップ4:使える結論を導き出す。
ある常識やルールに対してどのような態度をとるべきなのかということは、時と場合による。絶対的な答えなどはないのだから、戦略的かつ合理的に、よりよく生きるための結論を出さなければならない。
「コピペ」を考える
コピペはすべて悪いといえるのか?

ここからは「考え抜く力」を身につけるための具体的なレッスンとして、日常生活で身近な思考実験を体験してみよう。要約では、8つのレッスンのうち「コピペ」「同性愛」「AI」の3つをとりあげる。本書で示されるのは、あくまでも著者が考えた結論である。それが絶対的な答えでも、最終結論でもないことに留意したい。
まずは、「コピペ(コピー&ペースト)」についてだ。学校で出される課題やレポートでは、「コピペは厳禁」と何度も注意される。しかし、コピペはそんなに悪いことなのか。