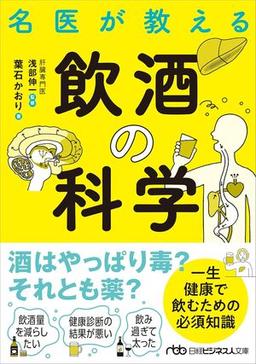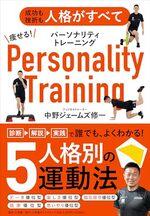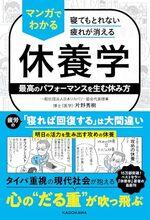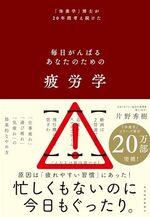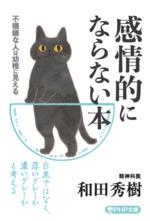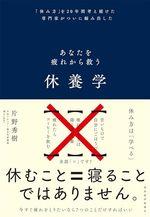飲む前に読む飲酒の科学
「酒の強さ」の正体とは(肝臓専門医・浅部伸一氏)

久しぶりにお酒を飲むと弱くなったと感じることはないだろうか。こう感じた人は、お酒に弱くなったのではなく、実は「元の強さ」に戻ってしまったのである。
酒に強いか弱いかは、アセトアルデヒドの分解能力で決まる部分が大きい。お酒を飲むとアルコール(エタノール)は胃や小腸で吸収され、主に肝臓で分解される。そして代謝を重ね、アルコール(エタノール)→アセトアルデヒド(人体にとって有害)→酢酸(人体にとって無害)という順番で変化していくことになる。
アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、少量のお酒でも顔が赤くなったり、吐き気をもよおしたりしてしまう。
一方、昔はお酒に弱かったが、お酒を飲み続けるうちに、お酒に強くなるということがある。こういう人は飲酒量が減ってくると「元の強さ」に戻ってしまう。
この理由は、アルコールを代謝する2つの経路のうち、1つの経路がお酒を飲み続けることで盛んに使われるようになるためである。
アルコール(エタノール)が酢酸になるプロセスは大きく分けて下記の2つの経路がある。
経路① アルコール脱水素酵素とアルデヒド脱水素酵素が使われる経路
経路② MEOS(ミクロゾーン・エタノール酸化酵素系)酵素群が使われる経路
アセトアルデヒドの分解が遅い体質でお酒に弱い人でも、飲酒を続けるうちにMEOSの酵素が誘導され、アルコール代謝に使われるようになる。その結果、お酒に強くなっていく。
しかし、MEOS代謝経路は薬なども含む異物を分解するためのものだ。したがって、MEOSが多く誘導されると薬の効果にも影響し、薬が効きにくくなったり、逆に効き過ぎたりすることがある。
二日酔いを防ぐかしこい飲み方(久里浜医療センター名誉院長・樋口進氏)
お酒を飲む上で、二度と経験したくないのが二日酔いだろう。
二日酔いを防ぐ大前提は、飲酒量を抑えることだ。加えて、お酒の種類によっても二日酔いの度合いが変わってくる。「色がついている酒」か「色がついていない酒」、「醸造酒」か「蒸留酒」によって、二日酔いのなりやすさは異なる。
ウイスキーとジンを同じ度数で同量飲んだ場合でも、ウイスキーの方が二日酔いになりやすいという報告がある。これは、色がついたお酒の方が、酒に含まれる成分が多いことに起因する。お酒に含まれる水とアルコール以外の成分はコンジナー(不純物)と呼ばれ、これが酒の風味や個性を決めている。コンジナーを多く含むお酒の方が、一般的には二日酔いになりやすい。