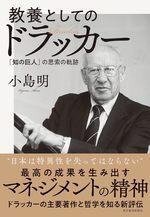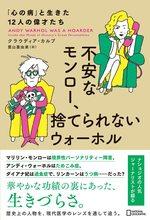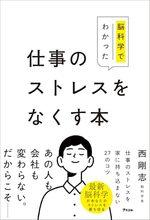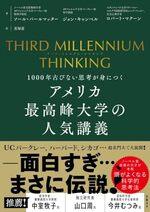梅子、留学す
父、津田仙
梅子の父、津田仙は欧米の学問や精神を取り込み、在野精神も持ち合わせた農学者・教育者だった。幕府の通訳として訪米し、半年ほどのアメリカ滞在で人生観が変わるほどの影響を受けたという。幕府崩壊後は官職を退き、外国人用のホテルに就職する。客の嗜好に応えるべく、西洋野菜の栽培を試み、梅子も毎日農園に出かけた。
仙はキリスト教に関心を抱いており、1875年に受洗しキリスト教徒となった。そして、彼が傾倒した反官僚主義的・反権力的な農政批判も、キリスト教と不可分であった。さらに仙は教育事業にも力を注ぎ、キリスト教精神に基づく私立学校の創設や運営に関わった。梅子の人生観は父親のキリスト者的啓蒙主義に強く重なるところがあり、また仙の築いた国内外のネットワークも彼女の人生に深い影響を及ぼすこととなる。
6歳にして海を渡る

北海道開拓使次官の黒田清隆はアメリカを視察した際に、アメリカ人女性の教養と社会的地位の高さに驚いた。それは教育によるものだと結論づけた黒田は、賢母育成を目的として、女子教育・家庭教育の必要性を訴えた。女子を官費留学生としてアメリカに派遣するという黒田の建議は政府に承認され、女子留学生の募集が行われた。アメリカに10年、費用は全て政府負担で奨学金も出すという条件である。そして渡航手段は、岩倉使節団に便乗するものとされた。これに津田梅子を含む5名が応募し、派遣が承認されることとなる。当時6歳の梅子を最年少に、最年長でも16歳と幼い少女たちは、父や長兄の決定によって異国の地へとほぼ強制的に送り出されていた。みな旧幕臣の出身であり、明治維新によって失った社会的地位を回復したいという思惑も働いていたと思われる。ただし、送り出した家族らは海外についてかなりの知識を有し、アメリカでの教育の意義を十分に認めていたうえでの判断であった。
こうして幼い梅子は、岩倉使節団の伊藤博文、大久保利通、岩倉具視、木戸孝允といった、錚々たる顔ぶれとともに海を渡った。梅子はヴィクトリア時代の白人中産階級のプロテスタント家庭たる、チャールズ・ランマン家に預けられることとなった。梅子は8歳の時に両親よりも早い時期にキリスト教の洗礼を受け、同じ留学生の山川捨松と永井繁子も後に入信することとなる。このほかの2人の留学生は、ホームシックにより1年足らずで帰国している。
1878年、梅子はハイスクール・レベルの私立女学校に通った。そこで17科目を履修し、とくに語学、数学、物理、天文で好成績をおさめた。育ての父、チャールズ・ランマンは梅子の聡明さに惜しみない賞賛を送っている。
帰国と葛藤
捨松と繁子は大学を、梅子はハイスクールを卒業してから、帰国の途についた。1882年に再び日本の土を踏んだ梅子は17歳、生涯の友として固い絆で結ばれた3人のうちただ一人大学教育を受けずに帰国した。
帰国後、梅子らは日本政府に失望することとなる。男子留学生とは異なり、梅子ら女子留学生にはなんの受け入れ準備もされていなかったのである。日本婦女の模範として賢母となることを期待していた日本政府の思惑と、日本女性の教育を使命として送り出されたと解していた梅子らの認識との間には、大きな齟齬があったといえる。