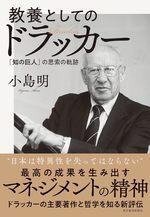「ケアする人」へのケアが必要とされる時代へ
経済的余裕を背景に作られた制度の限界
現在に続くような教育の仕組みや福祉制度が作られたのは、戦後まもなくのことだ。その後、日本は高度経済成長期を迎える。この頃の日本は、お父さんが稼ぎ手、お母さんが専業主婦となって、子どもを2人程度産み育てるのが一般的で、人口に注目してみれば“働く人”の割合が高まる「人口ボーナス」期であった。経済的余裕を背景に、この時期の日本では「国民皆保険」や「国民皆年金」などの制度が整えられた。
ところが、1990年代からの日本は、総人口における“働く人”の割合が低い「人口オーナス」の時代に突入した。少子化が進み、数多くいた“働く人”は“高齢者”となったのである。“働く人”が減ったため大人は仕事に駆り出され、家族や家庭の領域は後回しになった。つまり、ケアを必要とする人は増えているのに、働く年齢層の人が家庭にかけられる人手も時間も減っているのである。
家庭には家のことを担う余力がある人がいることを前提に考えられてきたこれまでの制度も、「ケアする人」をどう支えるかという視点から見直しの必要性が認識されるようになってきた。このままではケアしている人まで共倒れになり、次世代も育たないという事態になるということが、現実的な危機感をもって迫ってきている。
見えてきた「ヤングケアラー」という問題
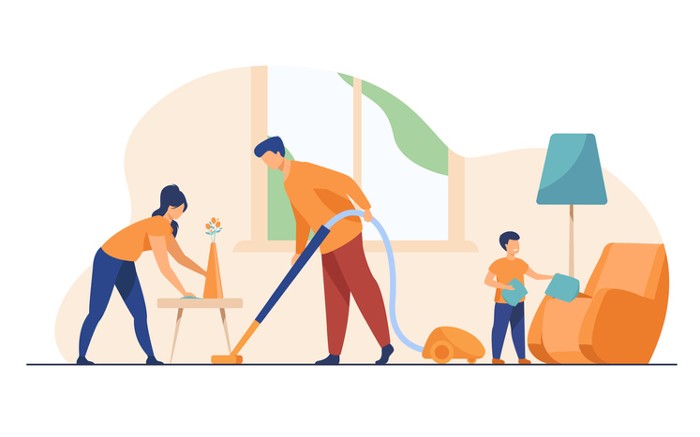
今の日本では、「家のこと」にかかる時間と手間を計算に入れずに、求められる「働き方」が決められている。働く大人を支えるために、裏方の家事や家族の世話を担う役割が、子どもや若い世代に担わされているのが「ヤングケアラー」の問題の一因といえるだろう。