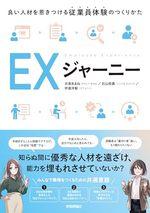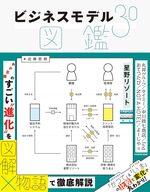雇用システム論の基礎の基礎
メンバーシップ型は「人」が基準

海外では、労働者が行うべき職務は雇用契約で明確に規定されている。一方、日本では、雇用契約に具体的な職務内容が記載されない、すなわち職務が特定されないことが一般的である。このため、日本の雇用の本質は、特定の職務(ジョブ)ではなく、組織への所属(メンバーシップ)にあるといえる。
ジョブ型社会の賃金制度としては「職務給」が採用される。その金額は職務評価という仕組みによって定められるため、ジョブ型社会における賃金は職務に基づいた固定価格制である。
一方、メンバーシップ型社会では、雇用契約で職務が特定されないために、職務を基準に賃金を決めるのは困難だ。その結果、職務と切り離して「人」を基準に賃金を決めるしかない。労働者が納得できる客観的な基準として、「勤続年数や年齢といった労働者の属性」を採用するのが年功賃金制である。その具体的な仕組みとして、毎年少しずつ賃金が上昇する定期昇給制が挙げられる。これらの性質から、この日本の賃金を「属人給」と呼ぶ。
とはいえ、現代日本の年功賃金制は、勤続年数や年齢による一律昇給を採用しているわけではない。この点を誤解している人は多いが、現在の日本の賃金制度の最大の特徴は、個別評価による賃金分布の分散にある。
ジョブ型社会では、一部のエリート層を除けば、一般労働者に対する人事査定が存在しない。あらかじめ職務記述書に書かれた職務に定価がついているからである。この社会における団体交渉や労働協約は、職種や技能水準ごとの賃金水準を企業の枠を超えて設定するものであり、数年ごとに大規模に行われる。
対してメンバーシップ型社会では、企業ごとに組織された労働組合が団体交渉を通じて労働協約を締結する。ただし、この協約は社員一人ひとりの賃金を直接決定するものではなく、企業全体の総額人件費の増加額を交渉する仕組みだ。
賃金の決め方
明治時代の賃金制度
明治時代の日本は、工業化が進み始めたばかりであり、労働市場の異動率は高かった。当時の平均勤続年数は1年程度であり、終身雇用制など存在していなかった。このように流動性の高い労働市場では、賃金は職種ごとに市場メカニズムによって決定されていた。
しかし日露戦争後、日本が重工業化の段階に入ると、雇用管理の仕組みに大きな変化が生じた。大規模な工場が自ら熟練職工の養成施設を設け、一から育成するようになったのだ。衣食住含めて企業が全額負担したため、職工は自分を育てた企業に忠誠心を抱き、長期間その工場に勤務する傾向が現れた。