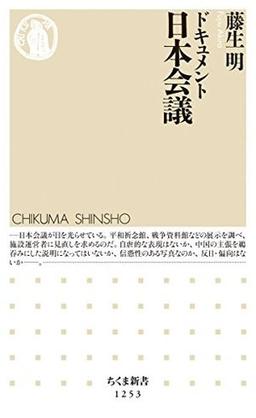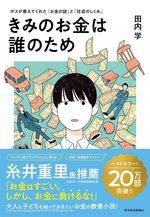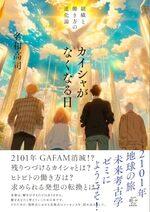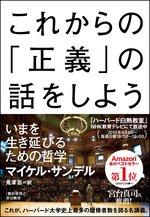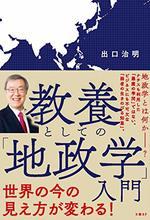日本会議の源流
打倒全学連からすべては始まった

今、憲法改正運動で、重要な役割を果たしているとされる「日本会議」が注目を浴びている。日本会議は今年で結成20年を迎え、その勢力を拡大している。
日本会議の源流は、1960年代の学園紛争だ。左翼学生がキャンパスを席巻していた長崎大学に、新宗教「生長の家」信者である椛島有三(かばしま ゆうぞう)と安東巌が入学したことが始まりだ。
当時、生長の家は、反共愛国・靖国神社国家護持・現憲法破棄と明治憲法復元を掲げる神道系の教団だった。生長の家の呼びかけで、生長の家学生会全国総連合(生学連)が1966年に結成された。
1969年には、右派学生の連合体である全国学生自治体連絡協議会(全国学協)が組織され、生学連がその中核を担い、安東が書記長を務めた。当時の大学では、三派全学連・共産党系の民青・革マル派と、左翼学生が活発に活動していた。椛島と安東はこうした左翼に対抗し、ビラ・新聞・講演会を駆使して、自治会を掌握した。この組織的戦術を全国に広げ、各地の民族系学生をまとめあげたというわけだ。
三島事件という衝撃
日米安全保障条約が自動延長となり、60年安保闘争が終結したことで、若者たちの政治の季節は終わった。1970年、椛島は民族派社会人組織「日青協」を結成した。
日青協の思想的支柱となっていたのが、国民文化研究会の小田村寅二郎、生長の家創始者の谷口雅春、神社新報主筆の葦津珍彦(あしづ うずひこ)と、作家の三島由紀夫の「四先生」だった。
ところが、三島由紀夫は「楯の会」の4人と共に自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪れ、益田総監を人質に取り籠城。割腹自殺を遂げてしまう。この三島事件が社会へ与えた衝撃は大きく、多くの右翼・民族派が三島の行為を賛美した。そして、70年安保闘争後に左翼が衰退し、敵を見失い停滞期にあった右翼・民族派全体が、この三島事件により息を吹き返した。
その後、民族派運動はスローガンを「反全学連」から「ヤルタ・ポツダム(YP)体制打破」に変え、「真の日本独立」を目標にすえた。YP体制打破とは、対米従属路線を否定し、反占領憲法・対米自立・自主防衛を目指す考えのことだ。
三島事件の裁判を通じて、民族派は「占領憲法破棄・明治憲法復元」を訴え、憲法改正論議を盛り上げようと活動した。しかし改憲論議は高まらず、裁判でも被告全員に実刑判決が下された。すると、支援者の間に失望が広まり、民族派の団体も四分五裂していった。
地方から中央へ

1975年になると、元号に法的裏付けがないことが政治問題となった。左翼政権誕生が現実味を帯びると、元号が空白になりかねない状況に危機感を抱いた日青協の椛島たちは戦略を大きく転換した。