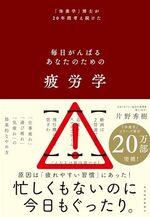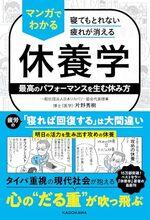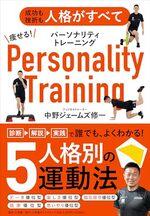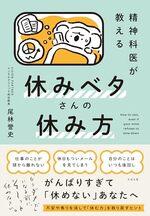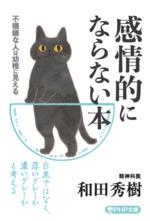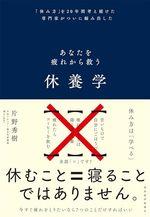「SIBO」とはなにか
日本人の小腸を襲う「SIBO」

小腸は、栄養分を吸収したり免疫力を司ったりする臓器だ。小腸が弱ると、免疫の力が落ち、風邪やインフルエンザといった感染症にかかりやすくなる。
健康的な小腸には、大腸と比べて細菌の数が少ない。これは、小腸の中で細菌が増えすぎないように防衛メカニズムが働いているからだ。加えて健康な小腸では、腸内細菌が多様で、免疫力が高いこともわかっている。一方、SIBO(シーボ)にかかった小腸では、爆発的に腸内細菌が増える。SIBOとは、別名を「小腸内細菌増殖症」という。大腸にあるべきバクテリアが小腸の中に入り込み、小腸に停滞してしまい、本来の居場所である大腸に移動しないときに起こる病気だ。
SIBOにかかった小腸の腸内細菌の数は、正常な小腸の10倍に及ぶ。さらには、腸内細菌の多様性が失われてしまうこともわかっている。そして、50パーセントのSIBO患者では、腸の粘膜の通りが良くなりすぎてしまっている。そのため、本来は通してはいけないはずの、細菌の作った毒素や未消化の栄養分まで通過させてしまう。その結果、さまざまな病気が引き起こされてしまうのだ。
【必読ポイント!】SIBOの症状
お腹の症状
腸内細菌が異常に増殖すると、細菌たちは大挙して食物を横取りするようになり、人間のほうが食物を消化しようとする前にそれを食い荒らしてしまう。人間の腸には栄養が十分にゆきわたらずに、水素ガスばかりが溜まることになる。腸内がガスで満ちると、腹部膨満感、ゲップになる。ガスが過剰になると、やせている人でも妊婦のようにお腹がせり出してしまう場合があるほどだ。
下痢と便秘
SIBOには、下痢型と便秘型がある。これらは病気が起こるメカニズムと症状が異なる。
下痢型のSIBOは、小腸の中で水素が発生しやすいのが特徴だ。われわれが発酵しやすい炭水化物を食べると、過剰に増殖した腸内細菌がそれをエサとして食べる。すると、炭水化物と腸内細菌が過剰な発酵を起こし、その過程で過剰な水素が発生するのだ。小腸は水素ガスに敏感であるため、水素ガスによってお腹がパンパンに張ったり、下痢になったりしてしまう。
便秘型のSIBOの特徴は、小腸の中でメタンガスが発生しやすいことだ。メタンガスを発生させているのは、「古細菌」という生物だ。これは細菌でもウイルスでもなく、細胞核を持たない単細胞生物である。
炭水化物や食物繊維をとると、腸内の細菌がそれを発酵させる。発酵によって発生した水素を古細菌が食べる。古細菌が水素を消費する過程でメタンが発生するのだ。
SIBOの患者が腸内に古細菌を飼っていると、メタンガスが発生し、便秘になりやすいことがわかっている。メタンガスが腸の動きを抑制し、腸内の物質を通過させる能力を鈍くするからだ。
なお、水素を発生するSIBOはやせ型の体型だが、メタンを発生するSIBOには肥満型の体型が多いことがわかっている。
ビタミンなどの吸収障害

SIBOにかかると、胆汁の働きが悪くなる。胆汁は、脂肪の分解を助ける消化液だ。胆汁の働きが悪化すると、脂肪が吸収できず、脂溶性のビタミンも吸収できなくなってしまう。
脂溶性のビタミンとは、ビタミンE、ビタミンD、ビタミンAだ。それぞれが欠乏すると、次のような症状が生じることがある。