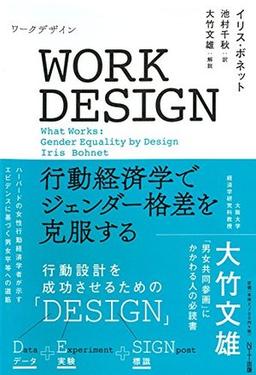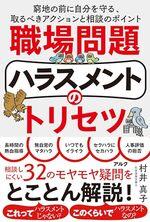行動デザインの力
カーテンの向こうのバイオリン

1970年代後半、アメリカの五大オーケストラでは、女性演奏家の割合がわずか5%にすぎなかった。しかし今、一流オーケストラでは、演奏家の35%以上を女性が占めている。こうした変化をもたらしたのは、「ブラインド・オーディション」の導入である。
これは、演奏家の採用試験で審査員と演奏家の間をカーテンなどで隔て、誰が演奏しているのかを、審査員から見えなくするやり方だ。有力オーケストラが相次いでこの手法を取り入れた結果、女性演奏家が採用される割合は飛躍的に高まった。
本来、演奏家の採否を決めるのは演奏能力のみである。人種や民族、性別などは関係ないはずだ。だが現実は違った。たとえば、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団には1997年まで、女性演奏家は一人もいなかった。そもそも、演奏家の採用を決める審査員たちは、楽団が白人男性のみで構成されることに、何の違和感も覚えていなかった。ましてや、自分たちがバイアスを持っているという認識もなかっただろう。
状況を変えるのに必要だったのは、問題についての認識と、一枚のカーテン、そして選考プロセスのデザインに関する決断だけだった。こうして採用候補者の母集団は、男性だけから男女両方へと2倍に拡大した。幅広い母集団から団員を選べることは、団員とその演奏の質を向上させ、オーケストラのビジネスにも好影響をもたらしたのである。
行動経済学のアプローチ
プロの演奏家は、演奏を評価される際に視覚的要素に強く影響されていることを知ると、たいていショックを受ける。音楽コンテストの審査員たちは、意識レベルでは音楽的要素を中心に評価しているつもりでいても、実際には視覚的要素に大きく左右されるという。演奏家が審査員の視界に入るという、審査プロセスという行動デザインは、審査結果に思いがけない影響を及ぼしていたわけだ。
バイアスは私たちの意識だけでなく、制度や慣習にも根を張っている。良いデザインは良い結果を、悪いデザインは悪い結果を生む。行動デザインは、リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンの名著『実践 行動経済学』では「選択アーキテクチャー」と呼ばれている。人々の行動を変化させるのに、法規制やインセンティブ制度を上回る効果が期待できる。
もちろん、法規制やインセンティブ制度も重要であるが、これらがいつも上手く機能するとは限らない。行動デザインは、人々がインセンティブに反応することを当てにせず、人々が自動的に望ましい行動を取るように仕向けるものだ。私たちは、自分自身や組織や世界のために好ましい行動をとれるよう、ときには、軽く背中を押してもらう必要があるのだ。
無意識のバイアス
システム1とシステム2

たいていのアメリカ人は、フロリダの住民のほとんどが高齢者だというステレオタイプを持っている。温暖なフロリダは老後の移住先というイメージが強いからだ。しかし実際には、フロリダ州の住民の82%が65歳未満で、この割合は全米平均の86%とほとんど変わらない。
フロリダと言われて老後生活を送る人々を連想するのは、代表的だと感じられる住民の属性(「フロリダといえば高齢者」)に基づいている。これは、「代表制ヒューリスティック」という思考バイアスの一つだ。
このようなバイアスによる発想や判断をしてしまうのは、思考がシステム1に支配されているからである。