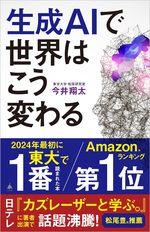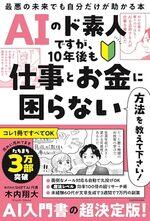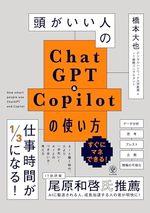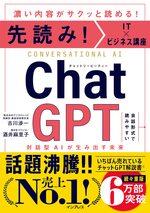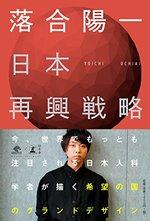新しい道具が、新しい私たちをつくり出す
デジタル前史

私たち現生人類(ホモ・サピエンス)の遺伝子の96パーセントは、最も近い親戚であるチンパンジーと共通している。私たちを人間としているユニークな4パーセントの主要な成分は、親指をほかの指と対置できるようにする遺伝子だ。この親指のおかげで私たちは「道具」をつくり、言語・文化・知識などの集団的な知性を生み出すことができた。
道具は、ホモ・サピエンスが進化したことによりつくり出された「結果」ではなく、私たちの進化を後押しした「要因」である。とりわけ「火」を使いこなしたことは、決定的に重要であった。火を食物の調理に利用することによって、胃の中で同じ量の食物を、より少ないエネルギーで処理できるようになった。その結果、体は余ったエネルギーを脳に回し、大きくなった脳はシェルター(風雨をしのぐ場所)や衣類、ハンドアックス(手に握って使う多用途の石器)などの画期的な道具を生み出した。そしてそれらのツールが、脳の能力を急速に増大させるという好循環を生んだ。
「変化」を超えて「進化」へ
いま私たちデジタルなサルが手にしているのは、コンピューターという新しい道具である。デジタルインフラのおかげで私たちはつながり合い、豊かになった集団的知性を使って、驚くほど幅広い問題に取り組めるようになった。
さらにこれからの10年で、極小のスケールで動作するナノマシンと量子コンピューターが本格的に導入されれば、私たちの個人的・社会的能力は、かつてないほど拡大するだろう。
私たちは自分の遺伝子・物理的実在・場所・時間、そして空間の性質をコントロールできる、新しいバージョンの人類に変化しつつある。これは単なる「変化」を超えた「進化」といっていい。
【必読ポイント!】 デジタルの光と影
ソーシャルマシン
「ウィキペディア」は人類史上最も包括的で、最も利用しやすい百科事典だ。こうした特長をもたらした要因として、メカニズムにワールド・ワイド・ウェブ(www)を採用している点が挙げられる。人間の能力とテクノロジーのパワーを結び付けて成果を生む仕組みを「ソーシャルマシン」と呼ぶが、ウィキペディアはその最も美しい例といえよう。そこでは人間の主導のもと、人間とテクノロジーがひとつの意識を持ったプロセスに統合されている。
ウィキペディアの編集ソフトは執筆者のマシンではなく、インターネットのページ上にある。創設者のジミー・ウェールズは、これをボランティア執筆者のコミュニティーに発展させた。それはインターネットの理念、振る舞い、テクノロジーにぴったりと合っていた。そこでは信頼性を高めるために、緻密なアルゴリズムも取り入れられている。こうしたアルゴリズムによって、テクノロジー自体がまるで生き物のように価値を加えたり、コンテンツを分析したり、編集したりすることができるようになった。しかしそれはあくまでも人間の意識と判断の下において実行されている。
AIは仕事を奪うか

AI(人工知能)については、いま2つの不安がささやかれている。1つはいわゆるシンギュラリティの問題だ。つまりAIがやがて意識を獲得する日が来るのではないか、そして私たちのライバルとなり、やがては人類に終わりをもたらすのではないかという危惧である。