【必読ポイント!】 「カッコいい」は“体感主義”である
語源は「恰好」にあり

「カッコいい」という言葉は、戦前の楽隊や軍隊で使われ始めた。そして1960年代のロック・ブームをきっかけに、人口に膾炙(かいしゃ)した。とはいえ「カッコいい」という日本語が、この時期に突然生まれたわけではない。その語源は「恰好(格好)」と考えるのが妥当である。
日本語学者の小野正弘によると、「恰好」という言葉が日本で使われるようになったのは中世後期だった。ただしそのときの意味は、「あるものとあるものとがうまく調和する・対応する」というものだった。これは今日でも「この議論をする上では、恰好の事例だ」といった用法に見ることができるが、この言葉は近世初期に至るまで、ほとんど一般的に使われていなかった。
近世中期になると「恰好」はさまざまな文献で見られるようになり、原義に加えて「全体的な見栄え・様子」(=外観)を意味する言葉として用いられるようになる。「恰好が良い」、「恰好が悪い」という言葉が随所で使われるようになり、「格好」という表記もこの時期に出てきた。この漢字の変化については、「恰」のもつ「さながら、まるで」というニュアンスの薄れとも関係しているのだろう。「不格好」「背格好」「年格好」といった複合語も生まれ、今日に至っている。
「恰好が良い」と「カッコいい」の違い
私たちが「恰好(格好)が良い」というとき、それは単に見栄えを指すとはかぎらない。そこには「あるべき理想像に合致しているかどうか」という価値基準がある。するとひとつの疑問が浮かぶ。絶対的に「恰好が良い」というのはありえるのか。もしありえるとすると、それを判断するのは誰になるのか。
結論から述べると、江戸時代や明治時代において「恰好が良い」という表現が用いられたとき、そこにはジャンルごとの理想像があり、そのジャンルの知識や経験が豊富な人の判断ほど重要視された。そしてその判断基準を理解するためには、「達人」との直接的な対人関係を通じて経験を積まなければならないとされた。その基準はあくまでも厳格だった。
ところが「カッコいい」という言葉の場合、マスメディアの隆盛によって、より開かれた場で用いられてきたという経緯がある。さらには第二次世界大戦後という事情も重なった。総動員体制から解放された日本人たちは、画一的な上からの押しつけではなく、別の基準を求めるようになった。ゆえに「カッコいい」の基準は「恰好が良い」よりも緩やかだ。スポーツカーとカラーテレビ、ネイマールとEXILE、エルメスの「バーキン」と困っている人をさりげなく助けること(!)は、すべて「カッコいい」に分類されうる。そしてそのなかで何が一番かを比較することも可能になる。
そういう意味で「カッコいい」は、「恰好が良い」から直接に派生した言葉とは言えない。なによりも「カッコいい」にあって、「恰好が良い」にはない意味合いがある。それは生理的興奮としての「しびれ」である。
「しびれる」という“体感”
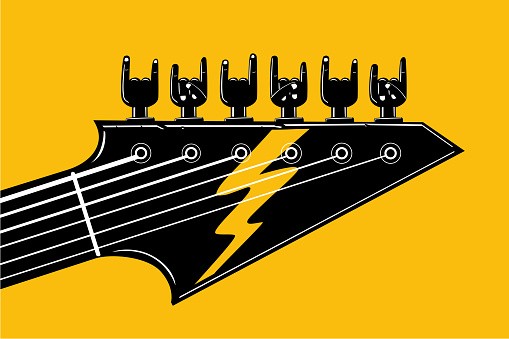
「しびれる」という体感は、「カッコいい」にあって「恰好が良い」にないものである。それは非日常的な興奮だ。私たちは「カッコいい」ものに憧れ、夢中になる。体が自然と反応したものに対して、反論することは難しいからだ。




















