【必読ポイント!】 日本はすでに先進国ではない
日本の社会や教育はガラパゴス化している

約150年間、我が国の教育システムは基本的に変わっていない。これは教育関係者以外にはほとんど知られていない事実だ。日本の教育制度は、明治から太平洋戦争まで続く富国強兵・殖産興業の国策を支えるべく、兵士や労働者を効率的に育成するのに最適化されたシステムだ。それゆえ敗戦で民主化された戦後においても、質の高い労働者を大量生産することができた。その結果、戦後日本は急激に復興・発展し、奇跡的な高度成長期を経て、20世紀末には世界で2番目の経済大国へ上り詰めるにいたった。
しかしここにきて急激に、この教育システムの制度疲労が明らかになった。GDP成長率で見ると、日本はほとんど伸びていないのである。この経済成長の停滞は、日本の教育システムの硬直化と完全にリンクしている。
一方で日本が停滞している間に、海外ではルールを変えて新しいゲームをつくる人たちが現れ、まったく新しい産業のプラットフォームを生み出したり、流通そのものを激変させたりしている。アマゾンを例に取ると、「本は本屋で買う」というルールが、「ネットで注文し、翌日には届けられる」というように変化した。音楽もデジタル化されてダウンロードで入手するようになったし、タクシーはスマートフォンのアプリで呼ぶのが常識だ。
世界では、そのような変化が同時多発的に起こっている。しかし日本人だけ昔とまったく変わらない仕組みの中、のほほんと暮している。教育は150年間変わらず、同じことを何回も正しく繰り返す能力を持った職業人が重宝され、記憶力テストで優秀な成績を収めた人が公務員や官僚になっているのだ。
学歴ではなく、学習歴へ投資しよう
学歴を考えるときに忘れてはいけないのは、「教育は投資である」という厳然たる事実だ。日本の場合、大卒は高卒に較べて、生涯年収が約6千万円多いというデータがある。しかしこれからは、単なる学歴ではなく学習歴、「貢献できる可能性や提供できる付加価値」を問われることになる。何が必要な投資かを見分け、最終的に自分の価値へと変換する能力、マネタイズする能力が欠かせなくなってくるだろう。
教育への投資を世界目線で長期的に考え、そこからのリターンを人生においてどう得るのか。その正しい方法論を学ばない限り、大学は出たものの、労働生産性の劣る未来のない日本企業で、大切な時間と人生を切り売りする生活に陥りかねない。
やがて文句を言わない大人しい日本人は、アジア企業からも安く買い叩かれるようになるかもしれない。それが日本の学生が直面している現実であり、しかも多くの学生が気づいていない現実なのだ。
変化に対応できる人材が必要になる

時代の変化は正確には予測できないし、10年後の社会で何が要求されるかは想像がつかない。だから日本が成熟しながらも活力を維持し、世界と対等に共存していくためには、「変化に対応できる人材」を早急につくらなければいけない。そのような人材を育成するには、学び方や働き方の変化を踏まえ、学び直すことが自由にできる社会であることが必要だ。
長いあいだ日本の教育システムは、「勝手に変化しない」「素直に命令に従う」「繰り返し能力の高い」人材をつくるのに長けていた。だがこの教育システムを、変化し続ける時代に対応できるものに変革しない限り、日本は早晩滅びることになるだろう。
世界に通用する人材の条件
英語で学ぶ、議論する、説得する
世界で通用する人材になるためにもっとも必要とされるのは、「英語を学ぶ」のではなく、「英語で学ぶ」ことである。

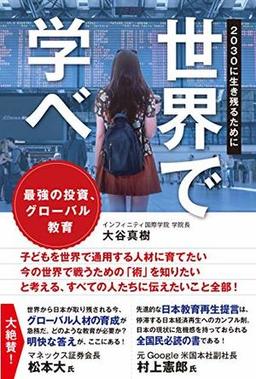















![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)


