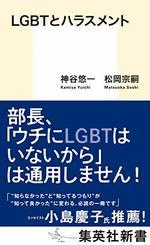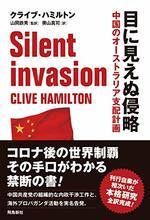「たくさんあること」は素晴らしい
個性があるから社会が成り立つ

雑草は勝手に生えてくるものだ。それなのに、育てるとなると難しい。品種改良されている野菜や花の種とは異なり、芽が出たとしても時期はバラバラだ。
「くっつき虫」という別名を持つ雑草「オナモミ」には、早く芽が出る種と、なかなか芽を出さない種の2種類の種子がある。芽を出す時期を変えることで、どんな条件下でも生き残っていけるのだ。
自然界においては、何が正解なのかは、そのときになってみないとわからない。だからこそ生物は、「個性」と呼ぶべき遺伝的多様性を持つようになった。
個性がなければ、環境の変化に耐えられない。実際に、アイルランドでは、病気に弱いが収量の多い「優秀な」ジャガイモだけを栽培した結果、その種が病気に侵されてしまい、壊滅状態になったことがある。
人間社会も、個性があるからこそ成り立っている。あなたの個性は、世界でたった一つのものだ。私たちの特徴は親から引き継ぐ染色体によって形作られるが、その組み合わせは70兆を超える。さらに、染色体を構成するDNAが変異することで、宇宙の歴史上唯一無二の、あなただけの個性が生み出されている。
ものさしでは測れない価値がある
人間の脳は、数値化し、序列をつけて並べることによって、複雑で多様な世界を理解しようとする。そのためのツールの一つとして作り出されたのが、平均だ。平均があるから、人間は大きさや長さを判断することができる。
平均に近い存在は、「ふつう」とよばれる。しかし実際の自然界には、「平均値」も「ふつう」もない。あるのは「多様性」だ。なかには、平均から大きく外れたはずれ者もいる。こうしたはずれ者がいるからこそ、環境の変化にも適応し、生き残ることができる。そして、はずれ者が新たな標準となって、生物は進化していく。
人間は、ものさしを使って優劣をつけたがる。だが、そこにあるのは優劣ではなく、単なる違いだ。ばらつきがなければ、種を存続させることはできない。
人間には、ものさしでは測れない価値がある。管理しやすい「ふつう」ばかりを評価するのではなく、もっと違いを大切にするべきだ。学校では「ふつう」であることを評価されるのに、社会に出たら「どうしてみんなと同じような仕事しかできないんだ」「他人とは違うアイデアを思いつきなさい」と言われるのは、なんとも皮肉なことではないだろうか。
境界が差別を生み出す

人間が物事を整理し、理解するために用いるものに、「境界」がある。本来、自然界に境界はない。すそ野が広がる富士山は、どこからどこまでが富士山なのか誰にもわからないし、昼と夜に境界はない。なのに、