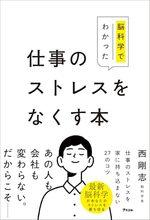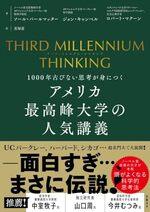世界最悪の発明リスト
アヘンとオピオイド系鎮痛剤

かつては「神の薬」として数々の病気の治療に用いられてきたアヘンであるが、今では個人には中毒を、社会には破滅をもたらすものであることを誰もが認識しているだろう。しかし、アヘンに匹敵する鎮痛効果を持つ薬物がないこともまた事実だ。そこで、多くの科学者は、アヘンの中毒性をなくし、鎮痛効果だけを残す方法を模索してきた。
モルヒネもヘロインも、そうした研究の成果として生まれたものだ。どちらも信頼がおける画期的な治療薬として製薬会社が販売し、広く治療に用いられ、後に大量の中毒者と死者を生み出すことになった。
近年では、同じくアヘンの成分から作られた医療用麻薬、オピオイド系鎮痛剤の蔓延が、米国において大きな社会問題になった。発端は、がん患者の終末医療に際し、痛みを和らげる目的で中毒性のある鎮痛剤を投与することが米国で認められるようになったことだった。その後、1986年に発表された論文で、疼痛(とうつう)管理の専門家がアヘン類縁物質の鎮痛剤の長期服用は比較的安全で、中毒性もなく、医師は鎮痛剤の使用をためらうべきではないと主張した。この論文に乗じた製薬会社が、1995年にオキシコチンという鎮痛剤を発売し、簡単に手に入る薬物として人気を博することになった。正常な使用では接種しきれないほどの大量の薬が全米で処方され、結果として多くの中毒者を生み出した。今世紀の最初の10年で、10万人以上が過剰摂取により命を落とし、交通事故を上回り、米国における事故死の最大の原因となっている。
マーガリン(トランス脂肪酸)
米国の国民病である心臓病。1950年代、大量の脂肪を摂取する国で心臓病の発症率が高いという調査結果から、脂肪が控えめの食事がブームになった。1977年には脂肪を総カロリーの30%に抑えるべきだとするレポートが上院委員会から発表された。じつのところ、脂肪の摂取量と心臓病の発症率の相関については裏づけはなかったにもかかわらず、脂肪摂取の制限は米国政府の正式な政策になった。







![[増補新版]活眼 活学](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F2598_cover_150.jpg&w=3840&q=75)