【必読ポイント!】モノづくりは人の心を動かす仕事
それぞれの関係性がモノを生み出す
モノづくりは、人の心を動かす仕事だ。組織のやりとりの中でも、自分がほんの少し行動を変えるだけで、モノづくりの流れは変わる。なぜならモノを生み出すのは、組織に所属する人々の関係性だからだ。人々がお互いに影響しあい、無数のコミュニケーションプロセスを経て、最終的な成果物が生まれるのである。
モノの価値は、人が利用してはじめて生まれる。社会現象を巻き起こし、多くの利益をもたらし、生活を一変させるモノは、人々の心を大きく動かしている。心を動かすモノを生み出すには、人の心をよく理解しながら、トライアンドエラーを繰り返していかないといけない。
モノを生み出すのは、結局のところ人間である。ならば、ともにモノづくりに参画するメンバーの心を理解し動かすことが、よいモノを生み出すための近道になるはずだ。
組織全員がユーザー中心主義になるには

現代社会はさまざまなモノであふれている。しかもネットが普及したことで、世界中から自分に合ったモノを選べるようになった。
ユーザーのニーズは、衣食住のような原始的でわかりやすいものから、人それぞれのニーズにあったものを選ぶように変わってきている。しかもいまのユーザーは、多様な流通網の中から、さらに多様なモノを選んでいる。だからこそそれをつくる側は、ユーザーを徹底的に理解し、常にユーザー視点に立つことが不可欠だ。
ユーザーは人間であり、組織も人間の集合体だ。ユーザーを熱狂させる価値をつくりたいなら、まず一緒に働くメンバーに価値を届けるところから始めるとよい。誰もがユーザー視点を持つ組織への変革は、組織の意志決定権を持つ社長や役員などのトップマネジメント層ではなく、むしろ現場のエンジニアやマーケター、プロダクトマネージャーなど、モノづくりに近い人々が起点になる。そこで生まれた小さな芽がチームに広がり、いずれは新しいユーザー価値を生み出すかもしれない。これが、組織全員がユーザー中心に視点をそろえ、モノづくりに取り組もうとする考え方だ。
ユーザーの声を鵜呑みにしない
求めるものを聞くことが大事
ユーザー価値を届けるためには、ユーザーの声を直接聞くのが早く確実な方法だと考える人もいるだろう。しかしユーザーは、自分が本当は何を欲しているのか、かならずしも理解していない。だからユーザーが「ほしい!」と言っても、そのまま鵜呑みにしてはいけない。人間は思った以上に自分の心を把握していないのだ。
ユーザー自身が気付いていないニーズを把握して、ユーザーの心や体験に働きかける価値を見つけ出すべきだ。やみくもに機能を追加するだけでは、価値は生まれない。機能面を向上させても、それが多くのユーザーにとって価値を持たなくなる瞬間がくるかもしれない。ユーザーの心を揺さぶってこそ、真価は生まれるのである。
ユーザー視点を手に入れる
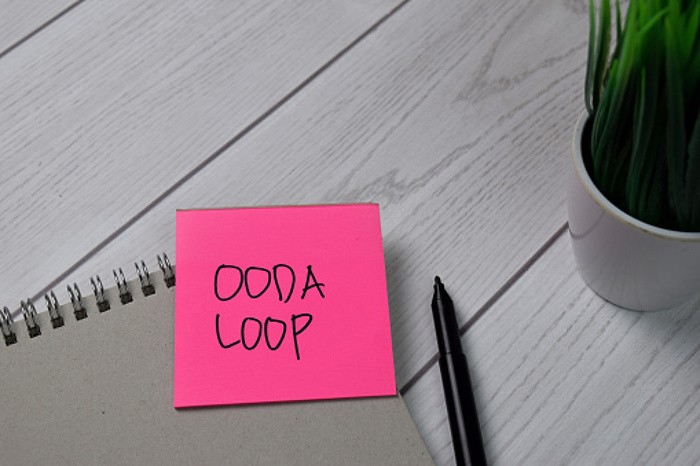
モノづくりの現場で、ユーザー視点を手に入れるために有効なのが




















