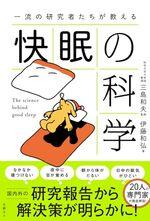生命の誕生と大絶滅
変化と選択
なぜ地球で生物が誕生したのかは、今でもわかっていない。46億年前に地球が誕生して以降、何億年もかけて生まれたたった1つの細胞が、現存する地球のすべての生物の始祖となった。それは偶然、というより奇跡に近いできごとだった。
その確率を表すのに、このようなたとえがある。「25メートルプールにバラバラに分解した腕時計の部品を沈め、ぐるぐるかき混ぜていたら自然に腕時計が完成し、しかも動き出す確率に等しい」――実際に起こったのだからその確率はゼロではない。
細胞は、細菌のような「原核細胞」から、ミトコンドリアや葉緑体と共生する「真核細胞」へと変化を遂げ、今から10億年前に「多細胞生物」が生まれた。その過程でも死んだ生物は分解され、作り変えられて入れ替わるという「ターンオーバー」を繰り返してきた。その「変化」の中で効率よく増えるものが「選択」的に生き残るという、「変化と選択」が生物の多様性を支えている。つまり「進化が生き物を作った」のである。
生物多様性

多様性が生まれてくると、ある生き物が他の生き物に居場所を提供したり、餌になったりするようになる。そうして生物間の関係が強まり、多くの生き物の生存を可能にする「生態系」が完成した。さまざまな種が存在して生態系が複雑になるほど、ますますいろいろな生物が生きられる正のスパイラルが働く。昆虫は植物の受粉を助け、土の中の微生物が動植物の死骸を分解する、というように。
こうした複雑な生態系は、環境の変動に強い。たとえば、ある種が絶滅したとしても、それと似た生存スタイルを持つ「ニッチ」の生物が代わりをするので、大きな問題は起こらない。絶滅で生じるロス(喪失)が生態系に吸収されるのである。
絶滅の連鎖
しかし、大量絶滅の場合は話がかなり違ってくる。たとえばヒトの活動の影響で生き物の10%が絶滅したとする。これは、数十年以内に起こりうると予測されている数値の上限である。これだけ多量に、しかも急激にいなくなると、似たようなニッチの生き物が抜けた穴を補うことがもはやできなくなる。
そうすると、それら絶滅した生き物に依存して生きていた生き物も絶滅するかもしれない。さらに、それらに依存していた生き物も絶滅し、ドミノ倒しのようにあっという間に多くの動植物が地球から消えてしまう。
そうなれば、人類にとっても深刻な食糧不足は避けられない。食料を巡って戦争でも起これば悲惨だ。大量絶滅は人類にも地球にも不幸以外の何ものでもない。
最も近くに起こった大絶滅は6650万年前(中生代末期白亜紀)のものである。生物種の約70%が地球上から消えたとされており、恐竜もこのときに絶滅した。しかし、そのおかげで、次のステージ、哺乳類の時代へと移ることができた。したがって、このときの大量絶滅は人類にとっては決して悪いことではなかった。しかし、次の大絶滅のあとに、私たち人類の子孫がそこにいるかどうかは予断を許さない。
生物はどのように死ぬのか
アクシデントか寿命か
「生物はなぜ死ぬのか」について考えると、「死」もまた進化が作った生物の仕組みの一部ということが言える。それでは、生き物の死に方にはどのようなものがあるだろうか。