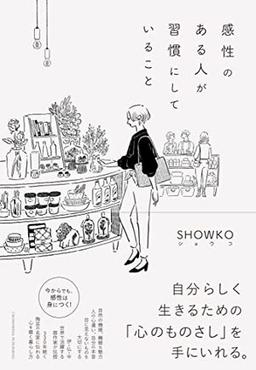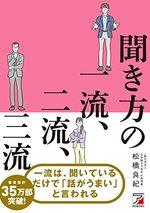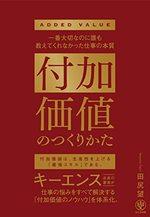1 / 6
【必読ポイント!】 感性を高めて「自分の答え」を出すために
感性は才能ではなく「習慣」で高められる
感性とは、ただ「センスがいい」という表面的なことではなく、その人の生き方そのものに関係している。自分の価値観で身につけるものを選んだり、他人への気遣いができて人間関係を主体的に築けたり、自分に必要なものを見極められたり。絶対的な正解のないことに、自分で答えを出せる人こそ、「感性のある人」だと著者は考えている。
「感性」は、生まれ持ったものではなく、日常の「習慣」によって高めることができる。著者は、京都の由緒ある窯元の家に生まれた。だが、生まれ持って感性があったわけではなく、アーティストをこころざしたのは20歳を過ぎてから。家を継ぐ立場ではなかったため、専門的な芸術教育を受けたこともなかった。しかし、現在では陶磁器の素材を用いた作品づくりや、ホテルのエントランスの装飾、オフィスの壁紙デザインの作成・監修など、「感性」を問われるアーティストとして活動している。ものづくりという正解のない世界では、つねに自身の「感性」を頼りに、正解を追い求めなければならない。その源泉は、これまでの習慣によって培われてきたという。
感性を高める「5つの習慣」

著者の周りの「感性のある人」は、「5つの習慣」を大切にしている。それは、「観察する習慣」「整える習慣」「視点を変える習慣」「好奇心を持つ習慣」「決める習慣」だ。