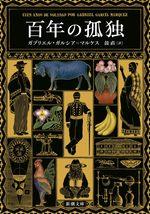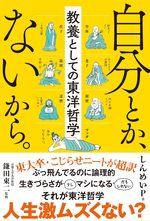【必読ポイント!】 著者の「美食」哲学
食事における3つの段階
食事には「①栄養摂取」「②うまい」「③美味しい」という3つの段階がある。「栄養摂取」は生存としての行為、「うまい」は本能としての欲求、そして「美味しい」は文化としての知的好奇心によるものだ。
本書は、食事を「栄養摂取」ではなく「人生を豊かにするための手段」と位置づけたうえで、「誰かの基準に振り回されずに、食事を楽しみたい」「絶えず更新される『美味しさ』の秘密を知りたい」「食の最前線で活躍する人の創意工夫に触れたい」と望む人に向けて書かれている。本書を読めば、食事を「知的体験」として楽しめるようになるだろう。
なぜ「外食」なのか

「フーディー」という生き方をする著者にとっては、世界中を飛び回り、現地の美味しい店で食事をするのが日常だ。南極から北朝鮮まで、世界127カ国・地域で食べ歩き、その体験をSNSや国内外のメディアで発信してきた。2017年度には「世界のベストレストラン50」にランクインしている店を制覇し、翌2018年度から6年連続で、「OAD世界のトップレストラン」のレビュアーランキングで第1位に輝いた。
食についての考え方は人それぞれであり、そこに正解・不正解はない。栄養補給ができればいい、お腹が満たされればいいという人もいれば、「何を食べるかではなく、誰と食べるかが大事」と考える人、自分で作って食べるのが好きな人、誰かに料理を振る舞うのが好きな人もいる。
著者自身は外食に特化しており、食を通して料理人というクリエイターの作品を鑑賞し享受するのがライフワークだ。ライブやフェスでアーティストのパフォーマンスを楽しむような感覚で、料理人のオリジナリティやクリエイティビティを楽しんでいる。
「美食」の再定義
本書における「美食」とは、必ずしも贅沢なものでも美しいものでもない。ニュアンスとしては「ガストロノミー(Gastronomy)」に近いだろう。
Wikipediaによると、ガストロノミーとは「食事と文化の関係を考察することをいう。料理を中心として、様々な文化的要素で構成される。すなわち、食や食文化に関する総合的学問体系」だ。要するに、文化的に食べること、すなわち「うまい」だけではない「美味しい」を探求することこそが、著者にとっての「美食」の定義である。
著者は、単にものを食べるのではなく、ものの背景にある歴史や文化を感じながらいただきたいと思っている。つまり、食べるという行為を通じて、多様な社会や文化を深く理解し、知的好奇心を満たしたいのだ。
美味しい味を楽しむだけではなく、どう美味しくしているのか、なぜその地で食べるのか、どんな歴史的背景があるのか、どんなストーリーがつむがれているのか……といったものを含めて食事を楽しむこと。著者にとって「文化的に食べる」とは、このような食事の仕方を指す。
高級店に通う理由
著者はしばしば「どうして何万円も払って、わざわざ高級レストランに行くのか?」と尋ねられることがある。