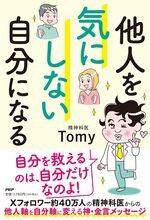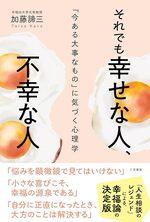【必読ポイント!】攻撃的で危ない「ピリピリ災害」
難クセの落石 ~粗探しをしてくる人
「手際が悪いな。営業何年やってるの?」「もう帰るの? ヒマでいいね」と難クセをつけてくる人。このようなタイプには、どう対応すればいいだろうか。
仕事上の注意なら反省しなければならないが、その言葉が人格否定などあなた自身を傷つけるものなら、真に受ける必要はない。
難クセをつける人は、心の底で「ありのままの自分」を嫌っている。とはいえ努力して成長しようという気もないため、他人を引きずり降ろして己を保とうとする。相手を否定していれば、存在しない自分の有能さ(仮想有能感)を感じていられるからだ。
防災方法としては、付け入る隙を与えないことだ。そして「さすが○○さんですね!」と持ち上げて、「敵ではない」ことをアピールして安心させよう。また、相手に恥をかかさないことも大切だ。このタイプは常に間違いを指摘されることを嫌うため、伝え方を工夫したい。
攻撃されたら「失礼しました」「承知しました」「すみません」と、受け入れ姿勢を示す「S言葉」でさらっと受け流そう。「ですが」「だから」などの否定を表す「D言葉」で反論すると、火に油を注ぐことになる。
キツい言い方落雷 ~すぐに感情的になる人

思い通りにならないと、イライラとキツイ言い方をしてくる人がいる。彼らはなぜすぐ感情的になり、人を委縮させるような物言いをするのだろうか。
イライラの理由はいくつか考えられるが、多いのは相手の期待値が高い場合だ。心理学では、「怒り」は第二感情で、その奥には怒りの原因、「期待」という第一感情があるといわれている。そのため、相手への期待が高いゆえにイライラして、手っ取り早く動いてもらう手段としてキツイ言い方をしてしまうのだ。
また、寝不足やプレッシャーなどで、脳疲労を起こしている可能性もある。相手をよく観察して、どちらのタイプかを見極めて対策をとる必要がある。
「相手への期待が高い人」に対しては、イライラしてきたら「この人は何を期待しているか」を探ることだ。素早く対応してほしいのか、丁寧に確認してほしいのか。その期待に応えるようにすれば、地雷を踏まずに済む。