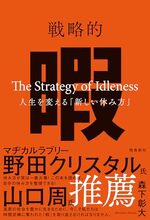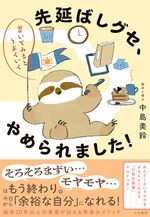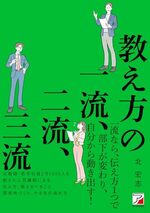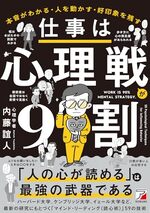チームが「まとまるリーダー」と「バラバラのリーダー」の習慣
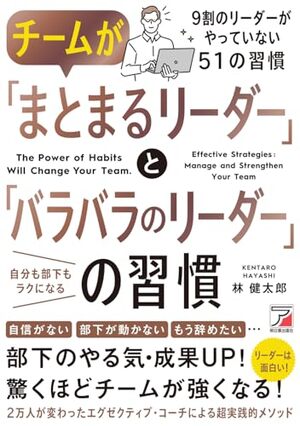
チームが「まとまるリーダー」と「バラバラのリーダー」の習慣
著者
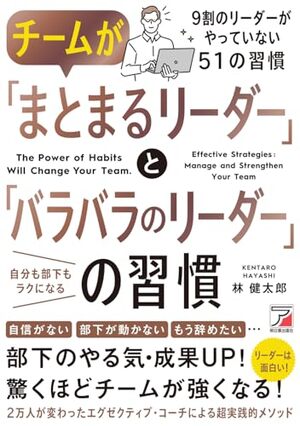
著者
林健太郎(はやし けんたろう)
リーダー育成家。合同会社ナンバーツー エグゼクティブ・コーチ。一般社団法人国際コーチング連盟日本支部 創設者。
1973年、東京都生まれ。バンダイ、NTTコミュニケーションズなどに勤務後、エグゼクティブ・コーチングの草分け的存在であるアンソニー・クルカス氏との出会いを機に、プロコーチを目指してアメリカで経験を積む。帰国後、2010年にコーチとして独立。これまでに日本を代表する大手企業や外資系企業などで、2万人以上のリーダーを対象にコーチングやリーダーシップの指導を行う。独自開発した「コーチング忍者」研修は、人的資本経営に必要なスキルとして(株)サザビーリーグ、(株)ワコールなどの企業に採用され、これまで1000人以上のリーダーが受講している。銀行の支店長向けエンゲージメント研修も多数手掛けている。チームビルディングの専門家としても活動し、多くのチームの再生に貢献。
企業向けサービス以外に、より良いリーダーになりたい方への個別指導プログラムも提供している。
『否定しない習慣』『子どもを否定しない習慣』(ともにフォレスト出版)、『期待しない習慣』(朝日新聞出版)など著書多数。
リーダー育成家。合同会社ナンバーツー エグゼクティブ・コーチ。一般社団法人国際コーチング連盟日本支部 創設者。
1973年、東京都生まれ。バンダイ、NTTコミュニケーションズなどに勤務後、エグゼクティブ・コーチングの草分け的存在であるアンソニー・クルカス氏との出会いを機に、プロコーチを目指してアメリカで経験を積む。帰国後、2010年にコーチとして独立。これまでに日本を代表する大手企業や外資系企業などで、2万人以上のリーダーを対象にコーチングやリーダーシップの指導を行う。独自開発した「コーチング忍者」研修は、人的資本経営に必要なスキルとして(株)サザビーリーグ、(株)ワコールなどの企業に採用され、これまで1000人以上のリーダーが受講している。銀行の支店長向けエンゲージメント研修も多数手掛けている。チームビルディングの専門家としても活動し、多くのチームの再生に貢献。
企業向けサービス以外に、より良いリーダーになりたい方への個別指導プログラムも提供している。
『否定しない習慣』『子どもを否定しない習慣』(ともにフォレスト出版)、『期待しない習慣』(朝日新聞出版)など著書多数。
本書の要点
- 要点1ミスをした部下には、「仲間」と「会社の顔」という2つの役割を使い分けて指導することが重要だ。共感する「仲間」としての姿勢と、改善を求める「上司」としての立場を明確に切り替えて伝えることで、部下の信頼と成長意欲を引き出せる。
- 要点2業務前の軽い雑談は、部下が仕事に取り組む気持ちを整えるための大切な「ウォームアップ」である。
- 要点3部下のやる気を引き出すカギは、昇進ではなく「キャリアビジョン」の対話にある。将来像を共有し、その実現のために今できることを共に考えれば、信頼と貢献意欲が育まれる。
要約
部下が自然と動く「コミュニケーション」編
「何を願うか」聞く

miniseries/gettyimages
チームがまとまるリーダーは「何を願うか」聞き、バラバラのリーダーは「何をするか」言う。
コミュニケーションの核心は「聞く」ことである。部下に対して「どんな仕事をしたいか」「どんなアイデアがあるか」と問いかけてみよう。
ここで重要となるのが「エンゲージメント」という考え方だ。エンゲージメントが高い状態とは、「自分が成功・成長できればOK」という姿勢ではなく、「自分の働きでチームや会社に貢献したい!」と感じている状態を指す。
リーダーの使命はエンゲージメントの高いチームを作ることであり、そのために有効な手段が「聞く」なのである。
エンゲージメントを高めるために必要なのは、「何をするか」ではなく「なぜするか」を語ることだ。すなわち、「自分たちは誰のためにこの仕事をするのか」という「存在意義」を示すことである。
とはいえ、あまり構える必要はない。気軽に「私たちの商品とサービスは、どんな社会問題を解決できるか」と問いかけてみてはどうだろう。
もっと気楽なテーマでも効果はある。あるお菓子メーカーでは、「自社商品の中でどのお菓子が1番好き?」という話題を出したところ大いに盛り上がり、普段は口数の少ない社員までもが商品への愛情や入社の動機を熱く語って、新たな提案まで出てきたという。
リーダーは、メンバーの「願い」を引き出そう。そのためにも、「どうなってほしい?」「どんなことが好き?」と問いかけ、部下の個人的な価値観に耳を傾ける必要がある。
部下への「聞く」を積み重ねる
チームがまとまるリーダーは部下への「聞く」を積み重ね、バラバラのリーダーは部下の事情を知ろうとしない。
エンゲージメントを高めるうえでもう1つの極意は、「聞く」を積み重ね、「小さな信頼」を着実に得ることである。

この続きを見るには...
残り3032/3793文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.07.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約