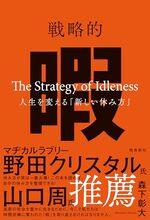「チーム」とは何か
「団体」と「チーム」の違い

2024年の夏に開催されたパリオリンピックの結果を分析して明らかになったのは、日本の選手たちは個人競技よりも団体競技で成果を上げているという点である。
例えば、フェンシング競技では、個人でのメダル獲得は1つにとどまったが、団体では4つのメダルを手にしている。陸上競技においても、個人の短距離100メートルでは決勝に進めなかったものの、リレーという団体種目では決勝進出を果たしている。
「日本人はチーム競技に強いのでは?」と思う人もいるかもしれないが、団体競技とチーム競技は別だ。実際、バスケットボールやバレーボールといったチームスポーツでは、日本は結果を残せていない。なぜだろう。
団体は個人の集合体、つまり、足し算だ。一人ひとりの力が1であっても、それぞれが自らの役割を着実に果たすことで、大きな力を出せる。
つまり、団体競技は、自分に課された役割を着実にこなし、指示や命令に「はい」と応えて遂行することで成り立ちやすい。一般論として、日本人はこのスタイルに適性があるように思われる。
これに対し、チームスポーツは掛け算である。1同士をいくら掛け合わせても、個の力以上にはならず、各個人の主体性と、それぞれの個性を最大限に活かす高度なコミュニケーション能力が不可欠となる。
日本社会では団体的な働き方が主流だ。しかし、このような働き方では、流動性が高く、先行きの見通しづらいグローバルなVUCA時代を生き抜くのは困難かもしれない。団体的な協調性に優れた働き方は、AIによる自動化や効率化に太刀打ちできないだろう。
AIの時代が到来した今だからこそ、人間にしかできない「真のチームワーク」を実現できるチームづくりが求められている。