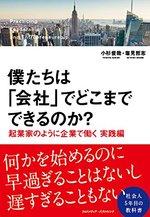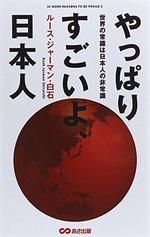市場と経済の成熟化を追い風にする
地元乳業メーカーからチーズ工房起業へ

赤部紀夫氏は北海道の地場乳業メーカーに定年まで勤務して独立し、ナチュラルチーズの工房を開いた。もともと、会社員時代、五十四歳のときに加わった、ナチュラルチーズの製品開発の新規事業がきっかけとなった。地元浦幌町のお土産になる乳製品をつくるというプロジェクトで、牛乳の製造現場でリーダーをしていた赤部氏は担当に立候補したのだ。
ナチュラルチーズは、全て手作りで、完成まで三週間ほどかかり、レシピ通りつくっても失敗することもあるという。こうした奥深さに魅了された彼は、自費で六回もフランスへチーズ研修に行き、「美しい自然とおいしい生乳がおいしいチーズを生む」という確信を得た。ところが、会社勤めでは思い通りにアイデアを具現化できないため、チーズ工房の起業を決心する。開業資金調達と工房の建設用地といった課題があったものの、彼は良い立地、家族の協力、おいしい水、日本屈指の生乳という好運に恵まれた。
起業した「十勝野フロマージュ」は、地元十勝の特産物や優良企業とのコラボレーションにより、ハート形のチーズなどの独自商品を次々開発し、順調に売り上げを伸ばす。地域の酪農家、大豆農家、養豚農家、レストラン、菓子メーカーなどと連携してこの土地でしかつくれないニッチ商品を成功させていったのだ。
融合戦略によって独自の個性をもったチーズは海外でも注目されており、グローバル・ニッチへの展開も見えている。
個性的な商品づくりを支えるもの
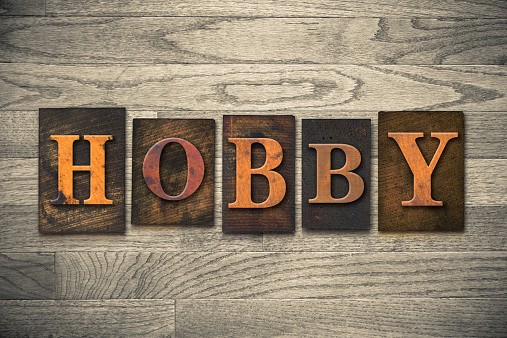
注目すべき点の一つ目は、赤部氏の勤めていた乳業メーカーはナチュラルチーズづくりから撤退したのに、赤部氏はこの分野に参入して成功した点である。
小規模な高付加価値型の「ホンモノ」商品の市場には、量産型、大企業型のメーカーが対応することは難しい。しかし、小回りの利く工房や小規模企業が個性的な商品を提供すれば、ニッチな消費者の支持を得ることができるのだ。
もう一つの注目要因は、赤部氏の趣味の多彩さと生き方である。彼は津軽三味線、社交ダンス、釣りに通じており、定年までのいわば一毛作目の職業人生もイキイキと楽しみ、そこで培ってきた視野の広さを、商品づくりにも生かしているのだ。
他産業との市場融合や技術融合といった戦略は、彼の「自分の興味や関心を大切に育てる」という生き方が支えているのだろう。また、好きなことに楽しむ姿を家族に見せてきたことは、シニアの転身にとって大きなハードルとされる「家族の理解」につながり、二毛作目の成功につながっていると言える。
大手企業で培った技術力を中堅・中小企業へ
エンジニアからコンサルタントへの転身
大手通信会社の機械系エンジニアだった鴫原正義氏は、早期退職制度を活用し、五十六歳でコネクターなどを手掛ける電子部品大手メーカーに転職した。そこでは、六十五歳まで商品開発プロジェクトの推進や知財戦略の進め方のアドバイスを行い、現在はコンサルタントとして、複数の中小企業にて、技術の標準化や特許の問題にかかわっている。開発スタッフの創造性の発揮を促すことが彼の役目である。
最初の転職の媒介となったのは、友人の奨めによる、人材紹介会社への登録であった。