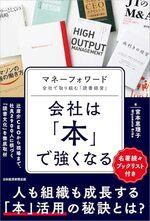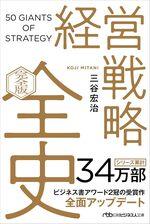ソーシャルメディアと炎上
そもそも炎上とはなんなのか
昨今におけるインターネットの急速な普及と多様なネットサービスの登場は、社会に大きな変革をもたらした。今やソーシャルメディアを利用すれば、不特定多数の相手に対して、個人が情報を発信することも容易である。コミュニケーションツールの利用率は、電子メールが約70%、ソーシャルメディアが約50%、無料通話アプリやメッセージアプリが約30%と伸びてきている。
しかしながら、コミュニケーションが活発になる一方で、1つの対象に誹謗中傷が殺到する、いわゆる「ネット炎上」が多発するようになってきている。本書では、炎上の定義を「ある人物や企業が発信した内容や行った行為について、ソーシャルメディアに批判的なコメントが殺到する現象」とする。
発生件数推移と傾向

2006年から2014年の炎上の発生件数をみてみると、2010年までは100件以下であったが、2011年には333件と急速に増えている。2013年の449件をピークとして、2014年には415件と減少しているが、これは炎上が社会的に注目されるようになり、一般人、著名人、法人関係がそれぞれ対策をとったり、より気をつけたりといった対応をとるようになったためではないかと考えられる。ただし、減少しているとはいえ下げ幅はわずかであり、今後増加に転じる可能性は十分にある。
また、炎上対象者を一般人、著名人、法人関係別の割合で見ると、法人関係が最も大きな割合であり、概ね50%程度を占めている。
さらに、Twitter、Facebook、その他(mixi、YouTube、価格.com、2ちゃんねる、その他のミニブログ)の割合では、2008年以降Twitterの割合が急速に伸び続け、2011年からは40%強で横ばいとなっている。FacebookよりもTwitterのほうが拡散力は高く、よりオープンなため炎上しやすい。したがって、炎上対策を考える際はTwitterを最も警戒すべきといえる。
炎上の分類と社会的コスト
炎上を分類する
本書では、(1)誰が、(2)何をしたか、(3)どういった対応をとったか、という3つの視点から炎上事件を分類する。
(1)については、「A:著名人」、「B:法人等」、「C:一般人」の3つに分ける。
また、(2)については、「Ⅰ:反社会的行為や規則・規範に反した行為(の告白・予告)」、「Ⅱ:何かを批判する、あるいは暴言を吐く、(政治・宗教・ネット等に対して)デリカシーのない発言をする。特定の層を不快にさせるような発言・行為をする」、「Ⅲ:自作自演、ステルスマーケティング、捏造の露呈」、「Ⅳ:ファンを刺激(恋愛スキャンダル・特権の利用)」、「Ⅴ:他者と誤解される」の5つに分けて考えた。
くわえて、(3)については「ア:挑発、反論、主張をとおす」、「イ:コメント削除」、「ウ:無視」、「エ:謝罪、発言自体の削除、発言撤回の発表」の4つに分けている。
炎上のパターン

(2)に注目すると、Ⅰ〜Ⅴの事例に共通しているのは、インターネットユーザの間にある規範に反した行為を行っているということである。批判、ステルスマーケティング、ファンへの刺激など、法律違反といえないような事象も、この規範に反していれば炎上対象となってしまう。
インターネットユーザへの批判、保守党への批判は特に炎上しやすい。また、食べ物・宗教・社会保障・格差・災害(不謹慎ネタ)・政治(特に外交)・戦争(安全保障)なども炎上しやすい話題といえる。
炎上の社会的コスト
炎上で行われるのは議論や生産的な対話ではなく、一方的な攻撃である。攻撃された側に有効な対処方法はなく、ただ傷つき、最終的にブログ閉鎖やアカウント削除して議論の場から完全撤退するしかない。