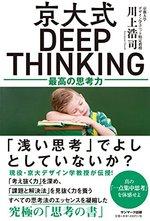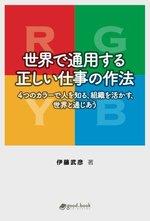シンプルで最強の思考ツール「5W1H」
成果を出す人は5W1H思考が標準搭載されている
視野を広げ、本質に迫る問いの源は「5W1H」の中にある。5W1Hとは、When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Why(なぜ)、What(何を)、How(どのように)という6つの要素から成る、情報整理のポイント群だ。常に成果を出す人は、この5W1Hを「くずして」「ばらして」あるいは、自在に「組み合わせて」使っている。
課題提起、問題発見・問題解決、創造的なアイデアの発想、説得力の問われるコミュニケーション。5W1Hは、こうしたビジネスのあらゆる場面でパフォーマンスを高めてくれる。シンプルゆえに使い勝手もよく、汎用性が高いという、まさに最強の思考ツールだ。ここからは具体的な使用方法の一部を紹介していく。
真の目的へさかのぼる「Big-Why思考」
思考をより高次元に導くBig-Why思考

ビジネスにおいて何らかの目的を定める際は、その目的が、より本質に近いものかどうかをよく考えることが重要となる。その際にキーとなるのが「Big-Why(さかのぼり)思考」だ。行動の目的を示すWhyを、普段認識しているレベルから深めて、より高いレベルにある真の目的やゴール、ニーズを押さえる。
具体的には、3段のピラミッド構造をイメージするとよい。最下層に行動や手段(やりかた)を表すWhat/How、2段目に理由(なぜやるのか)を表すWhy、そして最上位にBig-Whyが位置する。Big-Whyは「ありかた」や「どうありたいか」を表している。
人は普段、ピラミッドの下位2段、または最下層の手段のみで思考していることが多い。ダイエットを例に挙げると、毎日朝晩3キロ走る(What/How)→なぜなら痩せたいから(Why)という流れだ。一般的にはこれ以上理由を探ることはないだろう。しかし、Big-Whyを突き詰めれば、「心身ともに美しくなって注目されたい」「生活習慣病を防ぎ、健康を維持したい」といった、真の目的が見つかるかもしれない。そうすれば、問題解決に向けたアプローチ方法の幅が広がるにちがいない。
マーケティングにも役立つBig-Why思考

Big-Why思考はマーケティングでも大いに威力を発揮してくれる。ポイントは「モノ」から「コト」へ発想を転換することである。顧客は手に入れたものを使ってどんなことを実現したいのか。この視点が新たな価値を創造するきっかけになる。
「顧客が本当に実現したいコト」について、米国の著名マーケティング・コンサルタント、ジェイ・エイブラハムは、次のような例を挙げて説明している。
ある父親が息子に初めての自転車をプレゼントするために、店にやってきた。ここで父親が求めているものは何か。「モノ」の発想しかなければ、自転車と答えるだろう。しかし、「コト」にまで発想が及ぶと、彼の真の目的は、自転車の乗り方を教えるという人生で最高な経験を息子と二人で味わうこと(コト)だとわかる。
このように、顧客がモノを通じて描く未来の姿をイメージすると、時に顧客自身も気づかない本当のニーズが見つかりやすくなる。
これはマーケティングや商品開発のヒントになる。先述した例では、「自転車の乗り方を記載したパンフレットを作成する」「親子サイクリングセットを販売する」、あるいは「親子で参加できるイベントを開催する」などと、アイデアの幅も広がっていく。
Big-Why思考で顧客のニーズを「モノ」レベルではなく、経験的価値ととらえることで、アイデアの斬新さも高まっていく。
よりよいBig-Whyにたどり着くための3つの視点
Big-Whyを考える際に役立つのは、「ありかた」「ありがたみ」「あたらしみ」という3つの視点である。これらを意識することで、解決すべき真の目的に近づきやすくなる。
まず1つ目の「ありかた」とは、自分が何をするか(Do)ではなく、相手(顧客)がどういう状態で、何を実現しているか(Be)に視点を転換することである。
たとえば、スターバックスでは「コーヒーを販売している」というWhatレベルにとどまっていない。コーヒーを提供することで「顧客は心豊かになる、特別な体験ができる」などと、顧客のベネフィット目線で考えている。これが「ありかた」の視点を持つということである。
また、2つ目の「ありがたみ」は、他社には真似できない、顧客の満足度を高める価値を追求することである。ポイントは「自社の提供するものは、顧客にとって重要で、わくわくする価値にフォーカスしているか」「それはライバルとは一線を画するものか」という観点で考えることだ。顧客が120%ハッピーになれる状態をめざして、考え抜くことが求められる。
そして、3つ目の「あたらしみ」は、顧客に提供するものが、「顧客の生活や社会通念に変化をもたらすような革新的な価値」を生み出しているかどうかを確かめることである。Big-Why思考における最上級の視点といえる。
「あたらしみ」のある身近な例として、アイロボット社が開発した自動掃除機「ルンバ」が挙げられる。ルンバは、未知の空間でも自動的に自らの位置を特定し、自動で掃除をする。これにより、「掃除の負担から解放され、別のことに時間を使える」という時間的・心理的効用を、人々にもたらした。従来品の延長線上にはないイノベーションといえる。
このように、「ありかた」「ありがたみ」「あたらしみ」を意識することで、より面白くて、大きな価値をつくり出せる。
【必読ポイント!】 5W1Hで「思考のキャンバス」を広げる
漏れを防ぐ「俯瞰の枠組み」
ここからは、発想や思考の領域を広げる際に、5W1Hを最大限活かすための具体的な方法に触れていく。5W1H思考は次の2つのメリットをもたらす。それは思考の漏れを防ぐ「俯瞰の枠組み」と、発想を広げて独自の視点を得る「発想視野拡大のテコ」である。
まず、「俯瞰の枠組み」としては、企画書や提案書、そして報告書の作成において、論点や項目の漏れをチェックする際に大いに役立つ。私たちは、思いつきで仕事を進めてしまうことが多い。5W1Hに当てはめてみるだけで、漏れがないかが一目瞭然になるだろう。
一歩踏み込んだ問いに落とし込んで、組み合わせる

5W1Hを活用するには、「いつ、どこで、だれが」などの基本的な問いから、一歩踏み込んだ問いに落とし込むことが重要である。
たとえば、「いつ」を意味するWhenの場合はどうか。「いつから・いつまで」や「どれほどの時間」などと、時間・時期・期間を表す時間軸、あるいはプロセスや順番を表す過程軸とともに、柔軟に用いることで、より深い思考を巡らすことができる。同様に、「どこ」を意味するWhereについても、位置だけではなく場面、市場、販売チャネル(ルート)と柔軟に応用できる。5W1Hの各要素を自由自在に組み合わせていくことで、発想の精度を高められる。
何か企画をするならば、目的や背景(Why)、テーマ(What)、メンバーや協力者(Who)、スケジュール(When)、実施場所(Where)、段取り・進め方(How)、予算(How much)というように組み合わせるとよい。
新しい価値を見つける「発想視野拡大のテコ」
次に、「発想視野拡大のテコ」という機能について解説していく。
5W1Hでなぜ発想の幅が広がるかというと、5W1Hの問いを投げかけることで、これまでの延長線上ではなく新たな視点が加わるからだ。これは、次元の違う発想につながる。
たとえば、製品の改良を試みる際、製品そのものの性能や品質、すなわちWhat軸をいったん離れて、別の視点で再び考えてみる。すると新しい価値が見つかることがある。
この方法によって大ヒットとなったのが、パナソニックが開発した電動歯ブラシ「ポケットドルツ」だ。これまで競合他社は、ブラッシング力の強さや速さといった、電動歯ブラシの性能向上(What軸)に力を注いでいた。そんな中、パナソニックが注目したのはまったく別の視点だった。
きっかけは、パナソニックの女性社員の素朴な疑問にあった。「(自社は)電動歯ブラシを売っている会社なのに、なぜ社内では昼食後に手で磨いている人ばかりなのか」。電動歯ブラシがどこで(Where)、いつ(When)使われているのか。この点に本質的な問いを投げかけたことで、商機を見出すことができ、外出先用に特化したポケットドルツの商品化につながった。
そのほか、歯ブラシを使う人(Who)に注目することで、子供向けの電動歯ブラシという新たなセグメントを生み出した会社もある。このようにして思考のキャンバスを広げ、新たな価値を見つけられるのだ。
発想転換で新たな価値を生み出した事例に学ぶ

5W1Hを使いこなすには、既存の製品やサービスを見直し、新たな価値を生み出した事例を見て、「何を何に変えたのか」と考える練習が効果的である。
一例として、鉄道ターミナル駅などの構内にある商業施設、通称エキナカ(駅中)をとりあげたい。エキナカは従来の駅の何を何に変えたのだろうか。
1つ目は「駅の利用時間(When)」の概念である。単なる通過拠点(短時間)から、滞在拠点(長時間)へとコンセプトを大きく転換した。
2つ目は「駅の利用者(Who)」だ。利用者の定義を「電車を利用して移動したい人」から「移動する人に限らず、あらゆる人々」と対極的に変更したことが大きな事業転換を導いた。
これにより、駅(Where)そのものの定義も変わり、事業展開のアイデアがますます広がったという。従来の駅は、おしゃれなレストランやスポーツ施設、アミューズメント施設などが立ち並ぶ、非常に魅力的な場所へと生まれ変わることができたのである。
このように、5W1Hのシンプルな切り口で、対極的な概念を意識して整理すると、本質的な違いが浮き彫りになるはずだ。</p>