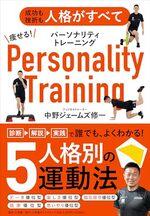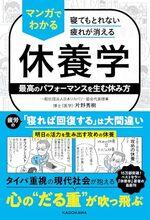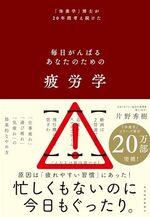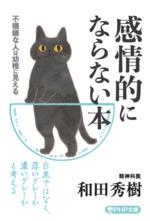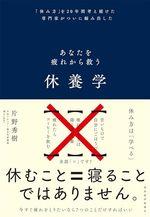本当に効く疲労ケア
「何となく不調」なときこそ東洋医学の出番
仕事や人付き合いに時間を割くことの多い現代人が抱える疲れは深刻で、自然に回復できる範疇を超えている人も多く存在する。そして、疲れは、放置すれば仕事のパフォーマンスや質を低下させるのみならず、寿命を縮めることにもなりかねない。疲れの放置は、「人生のリスク」なのである。
日本では「何となく体調が優れない」という理由で病院を受診する人が多いが、具体的な症状もなく病院に行くという感覚は「東洋医学」の影響を少なからず受けた名残であると言われている。じつはこの「何となく不調」な状態こそ、東洋医学の見地からすると、疲れをとるチャンスなのだ。「病気になってから対処する」西洋医学に対し、東洋医学は、「病気になる前に対処する」のである。
東洋医学で「疲れてもすぐ回復する」体をめざそう

疲れが積み重なっていくほどに体を動かすのが困難になるのは、新陳代謝が下がることが原因である。つまり、エネルギーの伝達や血液やリンパ液の流れが悪くなり、不要物が体から排泄されにくくなっている状態だ。東洋医学ではこのように疲れが溜まるイメージを「流れが滞る」という言葉で表現する。
「疲れやすい」とは「流れが悪い」ということであり、例えば一日中パソコンに向かって同じ体勢をとっていると筋肉的にも気分的にも停滞し流れが悪くなるが、30分に一度、ほんの10秒だけでも立ち上がったり姿勢を変えたりすることで、滞った「氣(新陳代謝)」が流れ出し、能率はよくなる。
ただし、活動すれば疲れるのは自然なことであるので、「疲れない」のでなく、「疲れていてもすぐ回復する」体をめざすべきだ。東洋医学では心身に起こる様々な変化を受け入れることで、よい状態が保てると考える。「しなやかに揺れながら元に戻る」ことを基本に、溜まった疲れを流す体質別のコツを掴んでいこう。
【必読ポイント!】体質別・疲労解消法
4つの体質で知るあなたの「体の個性」
疲れについて、本書の一番のポイントは、「誰にでも効く疲労回復法はない」ということである。「疲れ方や疲れの感じ方は人それぞれ」であり、メディアでステレオタイプ的に報道されている「疲れのとり方」は、体質によって合わなかったり、そもそも根本的な疲れの回復に至らないものであったりする。
体質は、傾向で大きく分けるとほとんどの人が4つのタイプのどれかに当てはまる。東洋医学では体の働きを5つに分類したものを五臓(肝・心・脾・肺・腎)と呼び、自然界の「木・火・土・金・水」という性質にあてはめている。本書では五臓から「心」を抜いた4つと対応する「木・土・金属・水」を扱い、タイプ分けをしている。これらは生活環境によって変化したり、人によっては2つ以上のタイプが混ざったりすることもある。さらにどのタイプも加齢によって徐々に「水」タイプの傾向が強くなっていく。
簡単に紹介すると、「木」タイプはリーダー気質のハードワーク型、「土」タイプはおっとりしたマイペース型、「金属」タイプは空気をよく読むロマンチスト型、「水」タイプは愛され上手の要領よし型だ。「木」タイプは過労になりやすかったり、「土」タイプは疲れやストレスが口の周りや胃腸の働きにあらわれたり、と、疲れ方もタイプによって変わってくる。
「いい感じ」という直感を大切にする
本書で紹介する「体質」は体の働き方の偏りのことを指す。根深い疲労であっても、体のクセが出ているだけなので、病院で検査を受けても異常が見つからないということがある。それだけに、健康と病気の境目にはいつも「自覚」というセンサーを働かさなければならない。