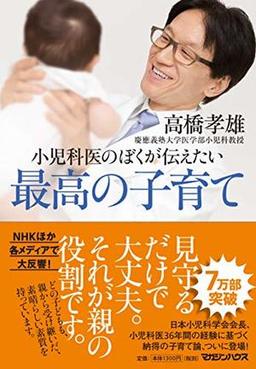【必読ポイント!】 子どもの個性と能力は親から受け継がれる
トンビがタカを産むことはない

子どもの個性、能力、才能は、両親から受け継いだ遺伝子によって約束されている。「トンビがタカを産む」ということわざがあるが、それは遺伝的にはありえない。「トンビ」に見える両親も、環境さえ整えば、子どもと同じ才能を開花させていた可能性が高い。つまり、遺伝子情報がもともともっている、正常な「振れ幅」に収まる程度の差でしかない。教育の効果とは、親から受け継いだ遺伝子の特徴を、上手に生かせるようにすることにほかならない。
たとえば、子どもの身長は、ある程度遺伝子で決まっている。両親の身長を、ある数式にあてはめれば、生まれてきた子どもの最終身長を予測することも可能だ。ただし、その身長にはだいたい8~9センチ前後のゆとりがある。
子どもの成長度合いが気になる場合でも、このゆとりの範囲に入っていれば、過度な期待や余計な心配をしなくてすむことが多いといえるだろう。
遺伝子の力で決まる本人の特性
人の特性のなかには、遺伝子の影響が大きいものもある。たとえば、飲酒に関しては、親の特性がシンプルに伝わる。その人が飲んで気持ちよく酔える量は、親から受け継いだ一対の遺伝子で決まっているからだ。もちろん、お酒に強いかどうかは、ある程度は飲酒習慣の影響を受ける。だが、どんなに鍛えてもお酒に強くならない人もいるのは、そのためだ。お酒が飲めない、体質的に合わないのは、遺伝子が決めた個性である。
また、運動が苦手なのも遺伝的な要素が大きい。「それならば早めに対策を」と思うのが親心かもしれない。だが、無理に子どもを体操教室などに通わせる必要はない。苦手なことを無理やりさせても、結局身につかないことが多く、子どもに劣等感を感じさせることが多いからだ。子ども側からやりたいといい出してからでも遅くはない。
遺伝子の力を発露させる環境や努力
「遺伝子が決めていることなら、努力は無駄」というわけではない。運動嫌いや勉強嫌いであっても、それが遺伝子の決めた個性だと認めたうえで、さまざまな角度からその子にあったやり方を探ることが重要だ。標準的なやり方を強制しないようにしたい。
トップアスリートでも、彼らの遺伝子がとびきり優秀とは限らない。オリンピックで活躍したフィギュアスケートの羽生結弦選手を例にとろう。たしかに、彼の運動神経やリズム感、手足の長さなどは、遺伝子の恩恵ともいえる。
しかし、羽生選手に、スケート選手になるための特別な遺伝子が組み込まれているというわけではない。あくまで正常な範囲に収まる遺伝子の「振れ幅」と、スケートを早くから習い始め、コーチに恵まれたといった環境要因の組み合わせの結果なのだ。大事なのは、その子が得意なことを一緒に見つけようという姿勢で、子育てをすることである。
情報に振り回されず、子育ての時間を楽しむ
心穏やかに過ごすことが大事

妊娠中は、幸せホルモンが多量に分泌される素晴らしい時期だ。そんなときに、おせっかいな人やインターネット上の情報に振り回されて、不安な気持ちになってしまうのはもったいない。不安になるくらいなら、情報に触れない方がよい。
小児科医の著者から見れば、妊娠中にした方がよいこと、摂った方がよい栄養などの情報には、根拠がないものや偏ったものが多いのだという。妊娠中の食生活はもちろん重要だ。しかし、食事に神経質になるより、おいしいものを食べて、穏やかに幸せにすごす方がずっとよい。
理想と現実の差が生む、子育ての悩み
母乳の素晴らしさを周囲に説かれて、「なにがなんでも母乳で育てなくては!」と自分を追い込んでしまう。そんな母親が著者のもとに来院することもある。著者は「母乳が出ないならミルクでよい」と答えている。