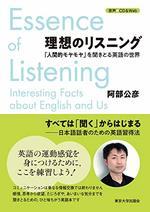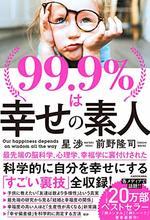日本人が絵と会計を嫌いになる理由
「制作重視」の教育の弊害

公認会計士の田中靖浩氏によれば、会計士や税理士は資格試験のための辛い勉強のせいで「勉強嫌い」になってしまう人が多いのだという。小学生のときの写生会で無理やり絵を書かされて絵が嫌いになってしまったという経験を持つ田中氏は、会計も美術も初期教育で失敗しているのではないかと指摘する。
東京画廊オーナーの山本豊津氏は、美術鑑賞は「見る」ことから「観る」ことに変化する形而上的な「かたちのない」事象であるのに対して、美術制作は形而下の「身体的な」作業であると指摘する。「観る」ことと「つくる」ことはまったく異なる行為であるが、日本の美術教育は制作することに重点が置かれ、観ることの大切さが疎かにされている。
この「制作重視」の問題は、会計業界にも見られる現象だと田中氏は言う。会計界でも「つくる」ことを勉強する簿記重視で、決算書を「観る」教育が疎かにされている。美術も会計も、「観る」教育を増やすべきなのかもしれない。
懐かしさと珍しさが「美しさ」をつくる
山本氏の考えるアートの源泉は、「懐かしさ」だ。あるものが文明の発展によって廃れると、それを懐かしいと思う気持ちが生まれる。部屋を片付けていたら小学生のときに遊んでいたブリキのおもちゃが出てきたとする。もう売られていないおもちゃに対する懐かしいという気持ちがアートになり、数百円だったおもちゃが数万円で売買されるようになるのである。そんな懐かしさを含む気持ちが山本氏の思う「文化」である。
モノが文化になるためには、一度捨てられないといけないとも言える。浮世絵は現在ではアートとして売買されているが、明治には山のように捨てられていた。そうして残ったものが時間を経てマーケットに出たからこそ、「懐かしさ」に「美しさ」が加わったのである。