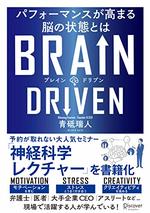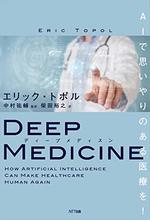Love Your Imposter
Be Your Best Self, Flaws and All
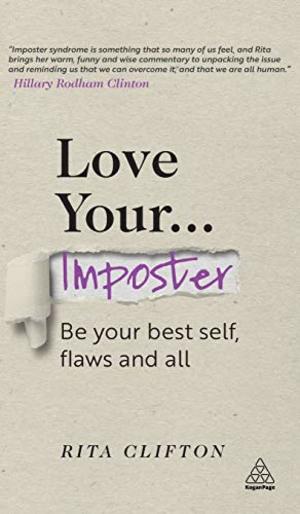
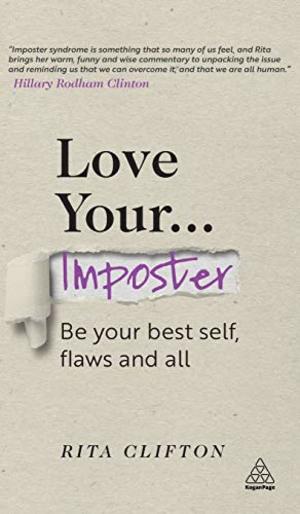
要約全文を読む
ログイン
著者
リタ・クリフトン (Rita Clifton)
サーチ・アンド・サーチのビジネス全盛期おいてストラテジー・ディレクター、後に副会長に就任。インターバンド(国際的なブランドコンサルティング・エージェンシー)のロンドン拠点で15年間に渡りCEOおよび会長を歴任。2013年にブランドコンサルティング会社ブランドキャップを共同創立し、近年、同社マネージメントグループに売却。世界各地の大手企業から新興企業まで、業界枠を越えてブランドコンサルティングを行う。CNN、BBC、SKYを含む数多くのメディアにてレギュラーコメンテーターおよびコラムニスト。CNBCの受賞番組Pop Up Start Upにアドバイザーとして出演。
民間企業数社の非業務取締役。WWF(世界自然保護基金)を含む非営利団体の評議員。イギリス政府による持続可能な開発委員会会員。
広告業界への貢献に対して大英帝国勲章を拝受。
著書に、ベストセラー Future of Brandなど。雑誌エコノミストのブランド特集に寄稿。本書Love Your Imposterは、著者のリーダー、コーチ、メンターとしての自己体験を基に、人間的なリーダー、特に数多くの女性リーダーの輩出に一助とならんことを目的として著作された。
サーチ・アンド・サーチのビジネス全盛期おいてストラテジー・ディレクター、後に副会長に就任。インターバンド(国際的なブランドコンサルティング・エージェンシー)のロンドン拠点で15年間に渡りCEOおよび会長を歴任。2013年にブランドコンサルティング会社ブランドキャップを共同創立し、近年、同社マネージメントグループに売却。世界各地の大手企業から新興企業まで、業界枠を越えてブランドコンサルティングを行う。CNN、BBC、SKYを含む数多くのメディアにてレギュラーコメンテーターおよびコラムニスト。CNBCの受賞番組Pop Up Start Upにアドバイザーとして出演。
民間企業数社の非業務取締役。WWF(世界自然保護基金)を含む非営利団体の評議員。イギリス政府による持続可能な開発委員会会員。
広告業界への貢献に対して大英帝国勲章を拝受。
著書に、ベストセラー Future of Brandなど。雑誌エコノミストのブランド特集に寄稿。本書Love Your Imposterは、著者のリーダー、コーチ、メンターとしての自己体験を基に、人間的なリーダー、特に数多くの女性リーダーの輩出に一助とならんことを目的として著作された。
本書の要点
- 要点1インポスター症候群とは、目的の達成や成功が明らかにもかかわらず、自分の実力を過小評価してしまう思考傾向をさす。
- 要点2キャリアの出発点は、あいまいでもかまわない。大切なのは、行動し、へこたれずに失敗から学ぶことだ。そうすれば、思いがけない方向性や出来事に遭遇できる。
- 要点3パーソナルブランドを作ろう。行動から外見に至るまで、自分自身を表現するのだ。そして目的を持ち、向上心を維持しながら、パーソナルブランドのバージョン・アップを図るのである。
- 要点4インポスター症候群は、とりわけ女性に多く見られる。より多くの女性が、リーダーとなって社会を改革していってほしいと著者は考えている。
要約
リタだってインポスター症候群
インポスター症候群とは?

KatarzynaBialasiewicz/gettyimages
「ハーバード・ビジネス・レビュー」によると、インポスター症候群とは、明らかに成功を収めたにもかかわらず、能力不足感や自己不信感を払拭できないことである。このような感覚は珍しいものではない。セレブやビジネスリーダーに至るまで、世の中の7割以上の人々の間で、インポスター症候群は蔓延しているという。
著者(以下、親愛を込めてリタと呼ばせていただく)も例外ではない。学生時代の試験や演劇発表に始まり、ビジネスパーソンになってからもミーティング、セールス、プレゼンなどで、すぐれたパフォーマンスをしたと思えたことがないのだ。
企業幹部となっても、「実力という点で、すぐに化けの皮がはがれる」という不安に苛まれてきた。それでもリタは、キャリアの頂点まで駆け上がった。とはいえキャリアの始まりの時点で、かならずしも明確なゴールが見えていたわけではなかった。
未来への足固め
学びはどんなことからも
リタは、秀でた知能を持ちながらも、世渡りが決して上手ではない父親に愛されて育った。しかし12歳の時、その父親が亡くなった。リタは家計を助けるため、週末や学校の休暇中にさまざまな仕事を経験することになる。
当時を振り返ると、決して悪いことばかりではなかった。ボーイフレンドを沢山見つけたり、地元の派遣会社について精通したり、多くの人たちと出会うことで、さまざまな人生があることを学んだりした。また、「お金は稼がなければ手に入らない」という現実を、身に染みて理解することもできた。
誰しも、世間には知られたくないことや、負の体験がある。しかし適切なサポートがあれば、ネガティブな体験もポジティブに変えられる――リタはそう確信するようになった。
ゴスのティーンエイジャーがケンブリッジ大学に

burcintuncer/gettyimages
リタは学業だとトップクラスであったものの、大学進学など夢にも考えていなかった。ミニスカートにパンダ目の化粧、ウエストまで伸びた髪という、1970年代に流行ったゴス・ファッションを地で行く、猫背姿のティーンエイジャーだったからだ。
教師のすすめでケンブリッジ大学を受験することになったときも、受験申込書の写真を見た教師が、「まるでセックス・クィーン」とため息をつくほどであった。それでもリタは、ケンブリッジ大学で古典文学を学ぶ機会を得た。
大学の初日、姉の夫の車で送られて登校したリタは、大学がひどく場違いである感じがした。実際、当時の彼女を指導した学部長も、30年後の彼女の姿に驚きを隠せない。
「成功のカギは何だったのか」と尋ねられても、リタは自分を成功者と思ったことがないし、賞賛されるほどの何かを達成したと感じたことがないという。これは決して謙遜からではない。
それでも大学は、リタにとって新しい自分と出会い、視野を広げる場所であった。大学に入学する前は、自分がどこに進んでいるのか、見当もついていなかったのだから。
いざ、社会人に
ケンブリッジ大学の就職斡旋は付け足し?
リタの感覚だと、ケンブリッジ大学でのキャリア指導は、アマチュアレベルでしかなかった。というのも、いわゆる上流階級の学生たちは、そもそも就職指導をあまり必要としていなかったからである。彼らには、すでにロンドンの金融市場のコネがあったり、政府機関やBBC、演劇学校、がんの研究所などへの道が開かれたりしていた。
一方でリタのキャリア志向は、通俗的であいまいだった。

この続きを見るには...
残り3032/4449文字

3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.02.09
Copyright © 2024 Flier Inc. All rights reserved.Love Your Imposter by Rita Clifton Copyright © 2020 Kogan Page All Rights Reserved. This Summary of Love Your Imposter is released by arrangement with Kogan Page
Copyright © 2024 Flier Inc. All rights reserved.Love Your Imposter by Rita Clifton Copyright © 2020 Kogan Page All Rights Reserved. This Summary of Love Your Imposter is released by arrangement with Kogan Page
一緒に読まれている要約