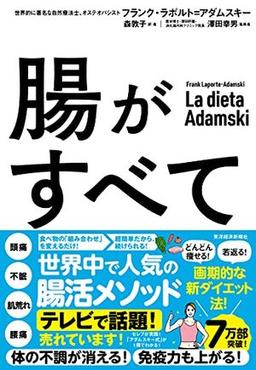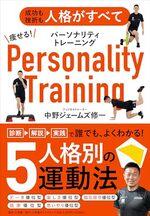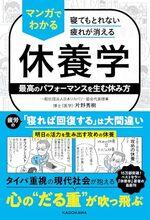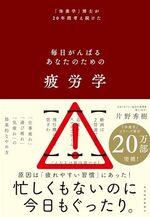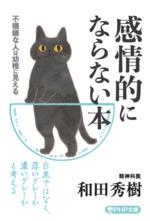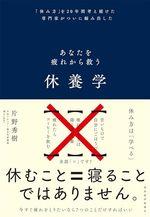体のすべてをコントロールする「腸の2つの流れ」を知る
「タテの流れ」と「ヨコの流れ」

腸は「管」だ。そのため「消化管」と呼ばれている。消化管の主な仕事は、物質を「ある点」から「ある点」へ移動させることだ。そのため、住宅の排水管と同じで、詰まるとうまく機能しない。詰まりを解消し、腸の本来の働きを取り戻すために生み出されたのが、本書の眼目である「アダムスキー式腸活法」だ。
消化管は、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸といったさまざまな臓器にまたがり、それぞれが連動して、2つの大事な働きをしている。その2つの働きとは「タテの流れ」と「ヨコの流れ」だ。
「タテの流れ」とは、余分な物質や有毒な物質などを体外へ排出する流れだ。主に毒素や体に悪い脂肪などが上から下へと運搬され、便と一緒に出ていく。
一方「ヨコの流れ」は、ビタミンやミネラル、体にいい脂肪といった健康に必要な成分を、血液を介して体中の細胞に送る流れだ。食べ物の中に含まれる体にいい物質は、消化管にある小さなヒダを通って血液に到達し、体に吸収されていく。
実は「ヨコの流れ」には、反対方向の流れもある。つまり、消化管の外側から内側へという流れだ。この機能により、血液中に存在している毒素を消化管の内側に排出して「タテの流れ」に乗せ、便や尿とともに出している。
この2つの流れが正常に働かなくなると、健康上のリスクが生じる。腸の重要な働きを認識し、腸と身体の関係をはっきりと意識しながら、健康リスクとその対処法を見ていこう。
本当に恐ろしい「7大健康リスク」
すべての体調不良の元凶は「腸の乱れ」にある
「タテの流れ」と「ヨコの流れ」は完全に依存しあっていて、「タテ」が詰まると「ヨコ」にも影響が出る。具体的にはこうだ。食生活が乱れていると、消化管の「タテの流れ」が滞り、消化管の壁に有害な汚れがたまる。壁が汚れで覆われると、消化管の穴が塞がれてしまい、「ヨコの流れ」が停滞する。その結果、食べ物がうまく取り込めなくなるとともに、血中の毒素が消化管内部に到達できなくなり、体中に回ってしまう。これが腸によって体調不良が起こるメカニズムだ。腸の状態が悪いと、思いもよらぬ深刻な影響がもたらされることがある。
腸の乱れで起こる「体の不調」の代表例
本書では、「腸の乱れ」によって引き起こされる体の不調について、代表的な7つの例を紹介している。「頭痛」「不眠」「肌荒れ」「腰痛」「コレステロール」「泌尿器の汚れ」「食道裂孔ヘルニア」だ。