【必読ポイント!】 激しく生きる中世人
「ふぉんのうじに、ふぃの手が!」
「母とは二度会うけど、父とは一度も会わないもの、な~んだ?」
これは戦国時代に書かれた『後奈良院御撰何曾(ごならいんぎょせんなぞ)』というなぞなぞの本に登場する問題の現代語訳である。正解は「くちびる」。「母」と発音するときには二度触れ合うが、「父」では一度も触れ合わないからだ。
現代日本話者ならば、首をかしげる説明だろう。「ハハ」と発音してもくちびるは触れ合わない。実は、戦国時代以前と以後ではハ行の発音が異なるのだ。戦国時代以前の日本語では「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」と発音されていたらしい。「母」は「ファファ」だったのである。時代考証をきちんとするなら、戦国ドラマは「ふぉんのうじ(本能寺)にふぃ(火)の手が!」「ふぁか(謀)られたか!」となるべきなのである。
江戸時代以降の日本人とそれより前の日本人とでは、言葉の発音ひとつとってもずいぶん異なっていた。そんな中世日本の言葉の問題に注目する。
日本語は悪口が少ない?
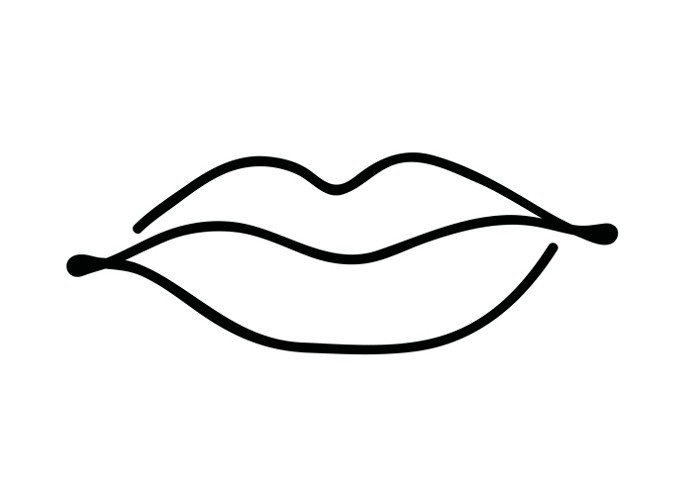
日本語は悪口や罵倒語のボキャブラリーが少ないことはよく知られている。しかし、これを「日本人は昔から人をけなさない温厚な民族だった」という論に帰結させるのは安易だ。鎌倉時代までさかのぼれば、現代では想像もつかないような強烈な悪口が数多く使われていた。
例えば、鎌倉時代の裁判史料に登場する「母開」という言葉は、かなり強烈な悪口だったようだ。この言葉が古文書に登場するのはわずか2回だが、いずれもこれを口にした側には高額の罰金が科されている。ではこの「母開」とはどのような意味なのだろうか。




















