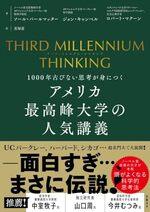自然状態における人間の権利
自然のなかでの個人
人はもともと完全に自由な状態にあり、自分の行動や財産、身体を思いのままにすることができる。他人の許可も必要ないし、他人の意志も関係ない。その点においてすべての権力は互いに平等なのである。
だからといって、自由をかたに何でもし放題というわけではない。自然状態におかれている個人は、「自然法」という決まりによって支配されており、その理性の声は、「何人も他人の生命や健康、自由、財産を侵害してはならない」と教えるのである。それというのも、人間は等しく神の所有物だからだ、とロックは書く。
二つの自由

人間が本来持っている自由は、地上のいかなる権力、人間の意志、立法権の支配に縛られることはない。それとは別に、社会における自由もある。
この自由は、国民の同意にもとづいて制定される立法権力にのみ制約される自由である。それ以外のいかなる意志の支配、法に制約されることはない。
したがって自由とは、「各人が自分のしたいように振る舞い、好きなように生き、しかもいかなる法律の拘束も受けない自由」ではない。むしろ、統治下での人間の自由は、「生活に際して守るべき恒常的な決まり」の下にあるのだ。
ひるがえって本来的な自由があるからこそ、人間は自分自身の生命に対する支配権を、何人にも譲り渡すことはできないのである。
所有権と労働価値
人間に生存の権利があるのは自然の道理だ。生きるために、自然界がもたらす物を体に取り込む権利がある。また個々の人間は身体という財産を所有しており、その身体が労働することで自然から取り出した物は、その人間の所有物という性質を帯びる。
その対象物に対してはもはや、労働した本人以外が手を出す権利はない。森で摘み取ったリンゴは、採取という労働によって、間違いなく共有の食糧と区別される。土地を開墾すれば、その分だけ所有する権利が生じる。
ただし食糧でも土地でも、労働が及ぶ範囲、その収穫物を使いこなせる範囲までが所有の限度となる。この決まりは依然として通用しているはずだが、貨幣に価値を置く暗黙の取り決めが成立したことで、必要以上のもの、余分な財産を所有する権利も確立した。
【必読ポイント!】 市民社会における統治
最大の目的は所有権の保存
聖書にもあるように、人間は共同体を作ることが運命づけられている。そして「人間が市民社会を作る最大の目的は、所有権を保全することにある」。では、政治的共同体の本質はどこにあるのだろうか。
この共同体が所有権を保全する権力をそなえるためには、どの構成員の犯罪も罰せられる権力が必要である。そこでは自然法の定めた私的な審判権は放棄され、一つ残らず共同体に委ねられる。政治的共同体はそうして内部のあらゆる紛争を解決しようとする。こうして共同の法と提訴先の裁判所が与えられた人々が、同じ政治的共同体を構成する人たちなのだ。
そうして立ち現れた国家に立法権とその執行権が付与される。
絶対君主制への批判
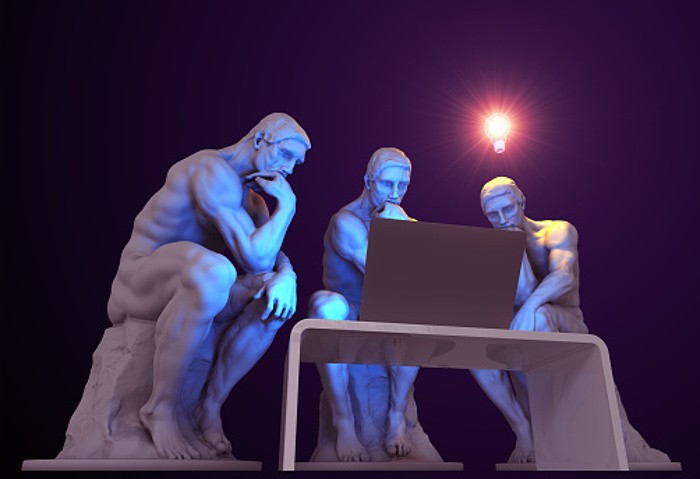
絶対君主制は、先述の市民社会とは両立しないし、したがって市民中心の統治形態には移行しようがない。市民社会は、市民が確立した公認の権威に対して、自然状態につきものの不都合を回避、あるいは改善するよう訴えられることが前提である。絶対君主は立法権力も執行権力も独占しており、この政治体制には中立かつ公正に裁く権威ある審判者は存在しないので、自然状態から脱することができていないのだ。
この場合、ふたりの人間が権利をめぐって争っても何も裁定されることはなく、ふたりは依然としてあらゆる不都合に直面したままとなる。そのうえ自分の所有権が君主によって侵害されている時、自分の権利について自分で判断、擁護する自由すらない。そうした臣民は理性ある存在としても認められていないようだ。
政治的社会:多数派の意思決定
複数の人間が一個の共同体、統治機構の結成に同意することでできた国家では、命令を下し制限を加える権利を多数派が握ることになる。
いかなる共同体も、一体の団体である以上、一つの方向に進まなければ機能しない。だから、多数派という大きい力の方向に進むことになる。こうして、共同体への承諾という手続きによって、多数派が制約を課すのだ。
これは、議決権が実定法で定められている議会において、多数派の議決が議会全体の議決として通る理由である。