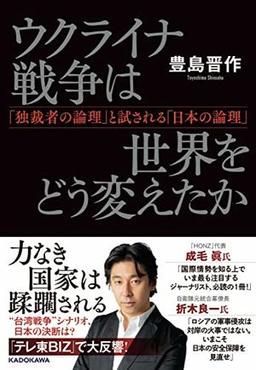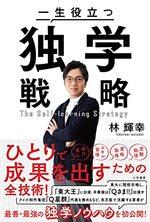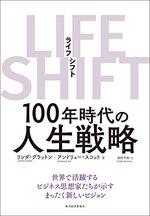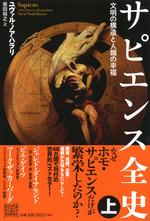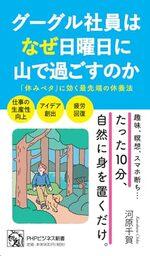ウクライナ戦争と核戦争シナリオ
「強者の戦術」をとれないロシア
ロシア軍によるウクライナ侵攻は、世界の軍事関係者に2つの衝撃を与えた。ひとつはロシアが本当に軍事侵攻に踏み切ったという事実そのもの、そしてもうひとつは、ロシア軍のあまりの弱さだった。ウクライナの首都キーウの陥落は叶わず、東部ドンバス地域でもウクライナ軍の激しい抵抗にあい、作戦の立て直しを迫られている。
その根本原因は、プーチン大統領も軍の指導部も短期間での決着を想定していたことに尽きるだろう。その前提が崩れれば、ドミノ倒しのように作戦計画も部隊運用も狂ってくる。つまりは戦略的ミスの部分が大きいのだ。
もっとも、最初はひどい戦い方をしながら、しだいに修正して盛り返すのはロシア軍の伝統だとする見方もある。
核使用という終末シナリオ

ウクライナ軍に武器供与などで協力するNATOを威嚇するため、ウクライナ侵攻以来、プーチン大統領は何度も核兵器の使用をちらつかせてきた。
政治的にも国際法的にも正当化できず、国内経済や自国軍が犠牲となるのにもかかわらず、プーチン大統領はウクライナの全面侵攻に踏み切った。苦戦と膠着を強いられる現在、核の使用に関してのみ合理的な判断をする保証はない。その点で、NATOの行動抑止に成功している。「気がふれている」と思わせる「マッドマンセオリー」だ。またロシアは、相手の勢いを削ぐために戦術核兵器を使用する「エスカレーション抑止戦略」をとり、核使用のハードルを下げてもいる。
最強の軍事同盟であるNATOが、同じ規模の打撃を与える「比例報復」を核で行えば、全面核戦争への扉を大きく開くことになるだろう。
ウクライナ戦争はなぜ起きたのか
ロシアはなぜウクライナを侵略し、ロシア人はなぜそれを支持したのか。あるいは、ウクライナのNATO加盟をどうしてそこまで嫌がるのか。
ロシアの行動の根底には、あまりに大きな「恐怖心」と「トラウマ」がある。ロシアは「おびえる国家」「被害者意識に囚われた国家」なのだ。
近代以降、侵略的なのは常に西欧諸国であり、ロシアはその犠牲者であり続けたというのが、ロシア人の歴史観である。
19世紀初頭には、ナポレオンに率いられたフランス軍がロシア帝国に侵略する。また、第一次世界大戦後に労働者階級による革命を実現しようとしたレーニン派(赤軍)に対し、それに抵抗する反革命勢力(白軍)を西欧諸国が支援するとともに、イギリス、フランス、ドイツが旧ソ連の各地を支配した。このとき日本もウラジオストクに上陸している。
こうした経験がロシアのトラウマとなり、欧米への不信感を募らせていった。
ロシアとそれに対峙する国の論理
なぜロシアはウクライナを侵略したか
この不信感、トラウマを決定的にしたのが第二次世界大戦の独ソ戦だ。人類史上、最悪の激戦ともいわれるこの戦争では首都モスクワも陥落寸前となる。
結局、第二次世界大戦終結までに、ソ連国民の死者は2700万人にもおよんだ。国民の7人に1人が犠牲になった計算だ。
独ソ戦の悲惨な記憶が、今日のロシア人の原点になっている。この戦いは容赦のない「皆殺しの戦い」であった。敵はウクライナやベラルーシを経由してロシア本土に侵入し、生命・財産を破壊しつくされた。だからこそロシア人は、外部からの侵略に対して恐怖心やトラウマを抱き、国境を接する東欧諸国がNATOに加盟することに抵抗し続けた。一方で、ヨーロッパの救世主であるという自負を持つに至った。
ベルリンの壁崩壊後の1991年にはソ連がワルシャワ条約機構(WTO)の解体を宣言する。しかし、NATOの不拡大を約束した外交合意は存在しない。バルト三国や東欧諸国は次々と自主的な判断でロシアを離れてNATOに加盟し、ウクライナでは親ヨーロッパ政権が樹立した。この流れは西側に対して友好的な姿勢を見せつつあったロシアを大いに刺激し、再びアメリカの強大な「敵国」としてしまった。
ウクライナ軍の急成長とNATO

2014年、ウクライナにあるクリミア半島がロシアに併合される。その直後、東部のドネツク州とルハンシク州は「人民共和国」として一方的に独立を宣言、実質的にロシアのテリトリーとなった。
この経験を経て、ウクライナはロシア人を兄弟と考える意識を変えた。所得の1.5%を「軍事税」として徴収し、古い装備は置き換えられた。ロシアの侵攻にウクライナが善戦しているのは、こうした努力の結果だという。
その奮闘の裏側にはNATOの支援もある。武器だけでなく、早期警戒管制機によって収集された情報などをウクライナに提供していると見られる。
そのNATOには、新たにフィンランドとスウェーデンが加盟する見込みだ。第二次世界大戦でソ連に侵攻されながら独立を保ったフィンランドと、200年間中立を保ってきたスウェーデン。両国が加盟の意向を示したのはやはり、「話のできるロシア」でなくなっているという警戒意識からだろう。
対ロシアでまとまれない国々の論理
ロシアのウクライナ侵攻を受けて、国連では40年ぶりに緊急特別会合が開催された。このとき、ロシア軍のウクライナからの即時撤退を求める決議案が採決されたが、その結果は複雑だった。アフリカ諸国の半数以上の26カ国が反対・棄権・欠席などでロシア非難に回らなかった。ロシアの理事国資格停止を求める決議に対しても、44カ国が賛成しなかった。
旧ソ連は西側の植民地だったアフリカ諸国の独立闘争や、南アフリカのアパルトヘイト打倒を支援した。それに、奴隷貿易の時代も含め、アフリカの人権を蹂躙してきたのは西欧諸国であった。だからアフリカ諸国は、ロシア除名の西側諸国の資格を問うたのである。
また、ロシアから軍事装備品や原油を輸入し、中国に対抗する観点からもロシアとの関係を維持したいインドも棄権に回った。西側民主主義陣営の力に一層のかげりが出ていることを印象づけている。
【必読ポイント!】 ウクライナ戦争は対岸の火事ではない
プーチン大統領暗殺は起こるか?
ウクライナへの軍事侵攻を決断したのはプーチン大統領であり、今後の戦争の継続に関しても、間違いなく最大の決定権を握っている。プーチンが暗殺されてしまえば、世界に平和が戻るのではないか。ウクライナの人々がそれを望んだとしても無理はない。