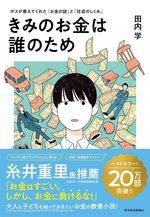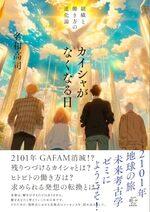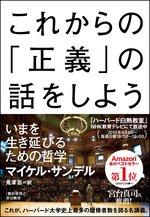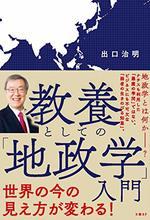時空を超えた「創造性の大学」
自由に思考できる場所

地下鉄アカサカ駅の改札を出てすぐに見える高層ビル。23階に広がる空間は、固定観念を取っ払って自由に思考できる場所、UNIVERSITY of CREATIVITY(UoC)=「創造性の大学」だ。
ここには、さまざまな属性のビジネスパーソンが集まる。靴を脱ぎ、昼間の自分も脱ぎ捨てると、漠然と心の底に眠っていた問いが浮かび上がってくる。「この生きづらさって、資本主義のせいなの?」「お金は欲しいけど、みんなは仕事に何を求めているのかな……?」
UoCは現代の人々が抱える悩み・問題を議論し合う学びの場だ。導きの礎としたのは歴史上の「巨人」たち。アダム・スミス、マルクス、ケインズ、シュンペーター、ヴェブレンといったお歴々の意識を、著書など古典の言葉を下敷きに、「現代ならばこう言うかもしれない」と仮説仕立てで展開していくフィクションである。カントなども登場し、経済学をやや離れ、社会学や哲学の領域の偉人らのものの見方や考え方も取り入れていく。
「そもそも、働くって何だろう」。今宵も誰からともなく呟きが漏れた。すると突然「その質問、私がお答えしましょう!」と声が響き渡る。声の主は「資本論」の著者、カール・マルクスだった。
そう、ここは時空を超えた教室。古代ギリシャの広場「アゴラ」のような学びの場に、歴史上の巨人や現存の世界の知性など多種多様な人々が自由に出入りする場だったのだ。
長いアカサカの夜が始まる。
今働くって、何ですか? ~労働編~
個人と社会を分断する分業
マルクスが語る。「現代は自らの仕事に不満・違和感を抱き、意味を見出せない“空疎な労働”が増え続けている。それは企業間競争の激化による過度な分業が、サービス業やソフト開発といった『第三次産業主体』の仕事にまで及んでいるためではないか。
本来、労働とは人間が自ら考える構想の作業、すなわち“精神的労働”と、実際に身体を動かす実行の作業、すなわち“肉体的労働”が統一されたものだった。しかし、会社組織が強固になるにつれ、この精神的労働と肉体的労働が分離されるようになる。