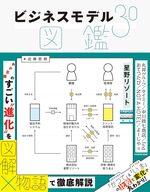戦略的な人的資本開示
3つのメガトレンド

2022年、日本の経済界において「人的資本開示」というテーマが大きく盛り上がっている。まずは、人的資本開示の背景で起きている3つのメガトレンドを紹介しよう。
1つめは、無形資産に対する金融市場の認識の変化である。2010年以降、投資家は人的資本を主な構成要素とする「無形資産」を重視する方向に変わっていった。アメリカのS&P500を対象とした企業価値の源泉を見極めるための分析によると、1975年には有形固定資産が83%、無形固定資産は17%だった。それに対し2020年には、無形固定資産が90%を占めている。ESG投資家が探しているのは、無形資産、特に人的資本を育むことにより企業価値の向上を目指す企業だ。人的資本の開示は今後の日本企業の経営のあり方を変えていくだろう。
2つめのメガトレンドは、人事領域へのクラウドテクノロジーの流入である。2010年代初頭より、人事領域でもHCMクラウドサービスを活用する企業が増えている。たとえば、S&P500の企業の半数が利用するワークデイは、労働集約的な業務の多くをクラウドで処理できるサービスだ。これにより、人事部門のスタッフは、戦略的な人事業務にフォーカスしていける。HCMクラウドサービスの浸透を背景として、人的資本マネジメント領域の国際標準規格「ISO30414」(人的資本開示ガイドライン)が生まれた。ISO30414の公表後、マルチステークホルダーに向けた開示を義務化する国が増えており、日本も急速にキャッチアップを始めている。
3つめのメガトレンドは、働き手の価値観の変化である。テレワークの普及も相まって、自分の意志で働く先を選び、よりよいキャリアを構築しようとする人が増えているのだ。企業と働き手は対等な立場で選び合う時代になった。経営者や人事担当者は、企業価値の向上に向けて、人事施策に働き手の価値観の変化を反映させる必要に迫られているのだ。
戦略的開示の効果
日本で本格化している人的資本の開示に対し、経営者や人事部門、IR部門の対応は次の2つに分かれることが予想される。
1つめの対応は、開示義務がある項目だけを最小限の労力で記述し、開示自体を目的とする「やっつけ開示」だ。人的資本経営の本質を省みることがないため、開示のボリュームと内容の質が低くなりがちだ。これでは人的資本経営のマネジメント品質の向上は期待できない。