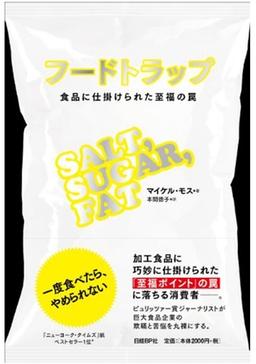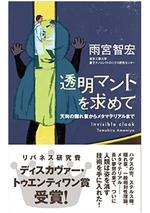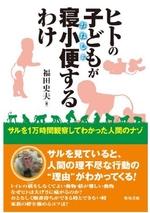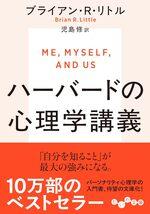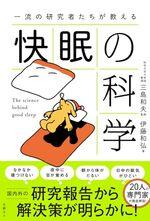糖分の甘い罠
麻薬的な糖分の魅力

糖分、脂肪分、塩分は、我々の体の中でどのような挙動を示すのか。それらへの欲求の背後には、どのような仕組みがあるのだろうか。
「糖分」の章では、まずラットを用いた研究が紹介される。1960年代、大学院生のアンソニー・スクラファニは、ラットが甘いシリアルを非常に好むことを偶然発見した。普段ラットは照明で照らされたケージの中央部分は本能的に避け、隅の物陰にいることを好む。しかし、ラットのシリアルに対する嗜好性を確認するために、スクラファニが甘いシリアルを中央に置いたところ、ラットは本能的な恐怖に逆らって走り寄り、シリアルをむさぼったという。その後もスクラファニはさまざまな実験を通して、糖分に魅了されるラットの行動を科学的に明らかにした。
人間に対する糖分の嗜好性を調べる研究としては、この後も本書に度々登場する、「モネル化学感覚研究所」の研究が紹介される。ここでは味覚に関する世界的な研究がされており、この研究所の研究費の半分、1750万ドルは大手食品メーカーが賄っているという。
研究所では、年齢・性別・人種によって甘味と塩味の感じ方が異なり、子どもとアフリカ系米国人が特にこれらを好むことを明らかにしている。
特に子どもは、急激に成長するエネルギーを必要としているので、甘味に強く反応する。糖分は、子どもの気分をよくする働きもするし、ヒトの進化の環境に甘いものが多くなかったため、口に入ると興奮を与えるのだという。
「もっと食べたい」の秘密

モネル研究所のジュリー・メネラは、5歳〜10歳の子ども356名を対象として行った研究で「至福ポイント」の存在に迫った。至福ポイントは、摂取したものを最もおいしいと感じる、脳に最も快楽を与えやすい量のことである。さまざまな原料に対して至福ポイントが存在し、売れる加工食品は、その配合を寸分の狂いなく至福ポイントに合わせたものだという。
甘味の場合、ある濃度でその快楽が頂点に達する。子どもの場合、この濃度は大人よりも高い。
同研究所は、糖分が過食を促すのかという研究も行った。研究結果としては、糖分単一では食べ物は魅力的な味にならないが、脂肪分と合わさるとより嗜好性が増すことがわかった。この二つに加えて、食べたいという脳の欲求を引き出す力がある成分は、ほかに塩分があるのだという。
清涼飲料水と食べる量の関連性の実験では、ラットも、人間も、甘い飲み物を与えると食欲が増した。人間の実験の結果では、定期的に甘味をつけた飲み物を与えることで体重が増加するという顕著な結果を得られた。
【必読ポイント!】成分を操る食品メーカー
コンビニエンスフードの功罪
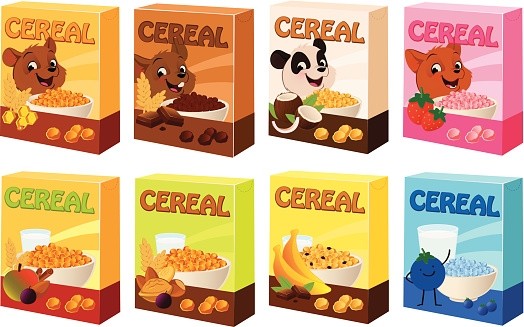
食品メーカーは、「食べたい」と思わせる麻薬的な作用を持つ糖分、脂肪分、塩分の配合を操り、「至福ポイント」を見つけ出し、ヒット商品をつくってきた。
さらに、加工食品メーカーは時代をとらえて商品開発を行った。外で働く女性が増えるにつれて、安価で簡便に準備ができる「コンビニエンスフード」の開発に焦点が当てられた。
たとえば、手軽に朝食の準備ができるシリアルは、こうした時代背景もあって、忙しい母親に歓迎された。とくに子ども向けの砂糖たっぷりのシリアルは、テレビ広告も効果を発揮して大ヒットした。子どもたちは、シリアルを喜んで食べた。
しかし、ある歯科医は異常に増え続ける子どもの虫歯に疑問を抱き、