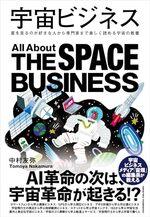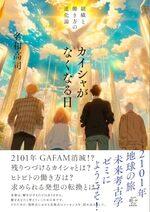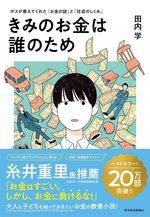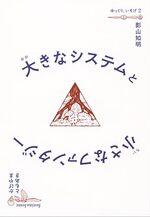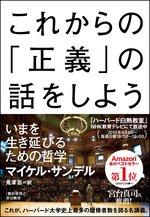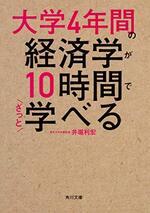情報とは何か?
情報が果たす役割
素朴な見方では、情報は「現実を表示する試み」であり、誤情報や偽情報はあくまでも例外的な失敗とされる。さらに、より多くの情報を集めれば自然に真実が見えてくるという期待がある。
しかし、実際の情報は単に現実を映すのではなく、異なるものを結びつけて新たな現実を創り出す働きを担う。正確性に欠ける情報が社会に流布しても、人々の信念を強く結びつけ、ネットワークを形成する力となり得るのだ。その点では、誤りや嘘、空想であっても情報となることがわかる。
こうした側面を踏まえると、情報は本質的に真実と結びついているのではなく、「物事を配置して構成された状態(イン・フォーメーション)にする」と言える。陰謀論のような現実の誤った表示でさえ、団結力のある新しい集団をつなげ、想像を超えた社会的変化を引き起こす引き金になってしまうのだ。
人間の歴史における情報

現実を正しく映すだけのものとして情報を捉えると、聖書や占星術のように重大な影響力を持った現象を説明しきれない。しかし、人々を結びつける「社会的なネクサス(つながり、結びつき、中枢)」とするならば、聖書が数十億もの人々を統合し、強大な宗教ネットワークを築けた理由も納得しやすくなる。
近代では、ドイツのナチスやソ連のスターリン主義のように、高度な技術のなかでさえ妄想的なイデオロギーによって国全体を短期間に統制した例もある。誤りや空想にもとづく主張であっても、それが集団を弱体化させるどころか、社会そのものを大きく動かしうることを示している。
こうして歴史を振り返ると、情報テクノロジーが発達して接続性が飛躍的に高まった一方で、現実の忠実な表示の方向には進んでいないのがわかる。サピエンスの成功は、情報から正確な地図を描く能力ではなく、情報を用いて大勢の人間を束ね、新たなネットワークを創り出す力量によると考えられるのだ。
そうして生み出された最初の情報テクノロジーが、物語である。
【必読ポイント!】 物語――無限のつながり
共同主観的現実
サピエンスが世界を支配するに至ったのは、特別に賢いからではなく、大集団で柔軟に協力できる唯一の動物だからだ。言語能力と脳構造の変化により、約7万年前から、虚構を語り信じる力を得た結果、同じ物語の共有による集団行動を可能にした。相手を個人的に知らなくても、同じ物語さえ知っていれば、無数の人と接続できる。これは現代のブランド戦略にも通じる。製品や人物に物語を結びつけ、現実の特性とは関係ないイメージを人々に浸透させる。
物語には客観的現実や個人の主観を超えて「共同主観的現実」を生み出す力がある。法律や企業、神、通貨などは、もともと物語が交換されるなかで生まれたフィクションであり、それによって人間は巨大な社会ネットワークを築いてきた。誰もがアメリカや中国の存在を疑うことはないが、イスラエルとパレスティナの紛争では、片側しか認めない政府もある。これは、国家が共同主観的現実であるという事実を浮き彫りにしている。