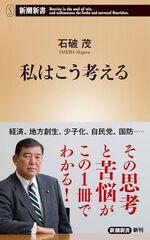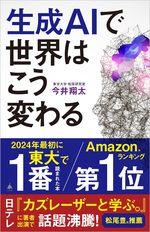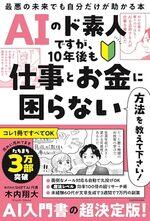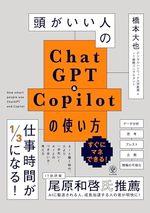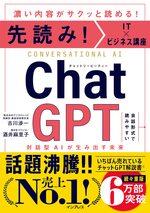過去の知能研究
そもそも「知能とはなにか?」

現在のところ、脳がどのように知能を生み出しているかははっきりとわかっていない。それどころか「脳の機能としての知能とはなにか」という定義さえ定まっていない。知能は脳の新皮質で生み出されていることについては、研究者のあいだで合意がとれている。しかし、新皮質が何をするのか、なぜ知能が実現しているかについては意見が分かれている。知能が脳の機能であることは古くから知られていたものの、脳の構造と機能の関係を特定することは困難であった。他の臓器とは異なり、解剖して脳を見たところで、どこが何をしているのかわからなかったのだ。
この状況を打開したのは、ある不幸な事故であったとされる。フィネアス・ゲージという米国の建築技師は、作業中に鉄棒が頭部を貫通する事故に見舞われ、事故の前後で大きな人格変容があった。前頭葉を損傷したことで性格が激変したことから、この部位が情動を制御するために重要な役割をになっているのではないかと考えられた。その後も実験により、どの部位がどんな機能を担っているかが決められるようになっていった。
しかし、このアプローチには根本的な問題がある。実際に観測しているのは「知能そのもの」ではなく、「知能が作用した結果」にすぎないからだ。ゲージの例では、実際に情動の不安定さが観測されたのではなく、情動が不安定になった場合に観測されるであろう行動が観測されただけだ。にもかかわらず、この観測から「前頭葉が情動に関わっている」と結論づけられた。「知能」を知能そのものではなく、「知能が働いた場合の行動の変化」でしか定義できないという問題は、生成AIで知能まがいの機能が実現した現在において、大きな混乱の原因になっている。
チューリングテストの限界
「脳の機能」として知能を研究する方針では、知能とはなにかをうまく定義できなかった。意外な方向からこの状況を打開したのは、コンピュータだ。
初期のコンピュータはごく簡単なプログラミングしかできなかったが、それでもある程度の知的作業をこなすことができた。これを用いて人工知能を作ろうとする科学者が現れるのも自然な流れであった。1946年に世界初の汎用コンピュータENIACが開発され、そのわずか10年後のダートマス会議で、人間のように考える機械が「人工知能」と名付けられた。
人工知能の研究には、工学的な開発だけでなく、知能の出現を解明するという理学的な目標もあった。しかし、知能の定義が曖昧なままでは、人工知能が知能を実現しているかの判断ができない。人工知能を作るなかで知能のよい定義が生まれるかもしれないという期待もあったが、知能が定義できなければ知能の実現は人工知能のふるまいをもとに判定することになる。