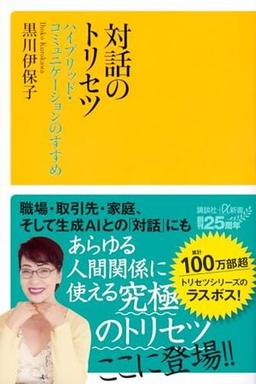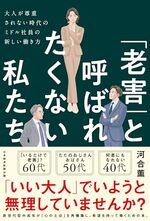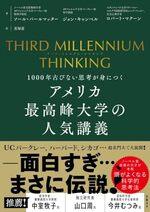脳に潜む二大特性
2つの「とっさのものの見方」
ヒトの目が遠くのものと近くのものを同時に見られないように、「とっさのものの見方」も、一度に「遠近両用」は難しい。
人類の「とっさのものの見方」は、「遠くの一点」と「近くを満遍なく」のたった2種類しかない。どちらも生きながらえるためには不可欠で、優劣もない。しかし、この特性の違いがコミュニケーションに大きな影を落としている。見方が異なると対話の手法も異なり、話が通じなくなってしまうのだ。
タテ型回路:遠くの一点に集中する

目の前の景色をざっと眺めて、危険なものや見慣れないものを発見したら、いち早く迎撃態勢に入る――。これは、脳の縦方向の信号(おでこと後頭部をつなぐライン)を使って行われる機能である。
この脳の縦方向を使う回路は、対象物との距離感やスピード感をつかんだり、位置関係やものの構造を把握したりする「空間認知の領域」において使われる。また、聴覚とも連携しており、野球選手の「ボールがバットに当たる音を聞いた瞬間、身体が動いている」というのは、この回路によるものだ。
敵や獲物、ボールが近づいてきたときに素早く的確に対処することは、この回路の得意とするところである。何万年もの間、圧倒的な危機管理能力で人類の狩りの能力を支えてきた。
本書では、この「脳を縦方向に使う、空間認知の回路」を「タテ型回路」、とっさのときに「タテ型回路をわずかに優先して、高頻度で使う」脳の状態を「タテ型優先」と呼ぶ。
ヨコ型回路:近くを満遍なく感知する
一方、脳の横方向の信号(右脳と左脳の連携信号)を強く使う回路「ヨコ型回路」もある。これは、「身の回り半径数メートル以内を感じ取り、些細な変化も見逃さない」働きをする。