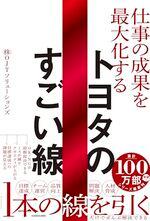あなたを苦しめる「決断疲れ」の正体
プロでさえ、決断に疲れる

英ケンブリッジ大学のサハキアンとカリフォルニア大学サンディエゴ校のラブゼッタの研究によると、人は1日に約3万5000回の決断を行っている。
この中には、「いつもの通勤経路を使う」「歯磨きをするときに〇回口を濯ぐ」といった無意識の決断も多く含まれる。そうした無意識の決断は決断全体の約95%を占め、残りの約5%が意識的な決断であるという。
3万5000回の5%は、約1750回だ。起きている時間を約17時間と仮定すれば、1時間あたり103回もの決断を下している計算になる。
ここで注目したいのが、「決断疲れ」という現象である。意思決定やセルフコントロールといった行為を続けることで、決断疲れが生じると、その後の作業における集中力やパフォーマンスが大きく損なわれる。
決断疲れを理解するための代表的な実験として、スタンフォード大学経営大学院のレヴァヴとイスラエルのネゲヴ・ベン=グリオン大学のダンジガーらの研究結果を紹介したい。イスラエルの刑務所で1年間に下された仮釈放に関する判断を分析したところ、可否を分ける要因は受刑者の人種や犯罪内容ではなく、審査された時間帯であることが判明したという。
具体的には、午前の早い時間に審査を受けた受刑者の約65%が仮釈放を認められたのに対し、時間が進むにつれて許可率は低下していき、裁判官の休憩後には再び65%に戻った。決断のプロである裁判官でさえ、時間と共に決断疲れに陥り、判断力が低下していたのである。
選択肢が多すぎると、人は諦める
レヴァヴは、アイエンガーらと共に、新車購入を検討する750名を対象とした実験も実施している。
この実験では、被験者を次の2つのグループに分け、内装色や外装色、バックミラーなどについて、数ある選択肢の中から選んでもらった。
グループAは、選択肢の多い項目から順に選んでいく形式である。具体的には、56種類の内装色、26種類の外装色、25種類のエンジンとギアボックスの組み合わせ……と続く。
一方、グループBは、選択肢の少ない項目から順に選んでいく。4種類の変速ノブ、4種類の内装スタイル、6種類のバックミラー……といった流れだ。
その結果、グループAの被験者は、途中で「もうデフォルトでいい」と諦める傾向が強く見られた。対照的に、グループBの被験者は、最後まで自分で選択を続けることができたという。
この実験結果は、「選択肢が多すぎること」が、人にとってどれほど負担になるかを示している。
完璧を求める「不安」が決断を妨げる
決断疲れを語るうえで、忘れてはならないもう一つの要因が「不安」である。
たとえば、国内旅行の計画を立てる際、多くの人は予算の確認、美味しい食事のリサーチ、特別な体験の検討など、膨大な情報を集めることになる。
そのプロセスの中で、あれもこれもと比較しすぎて決められなくなり、最終的にはすべてが面倒に感じてしまった――そんな経験はないだろうか。
こうした「情報を集めすぎてしまう」行動の背景にあるのが、不安という感情だ。絶対に失敗したくない、完璧な選択をしたいという思いが、過度の比較や検討を引き起こしてしまうのである。
【必読ポイント!】 決断を楽にするには?
決断に時間をかけすぎない

正しい判断を導くには、決断に時間をかけないことが有効である。
オランダ・アムステルダム大学のダイクスターハウスらによる実験では、被験者に4台の中古車を提示し、そのうち1台だけ明らかにお買い得な車を紛れ込ませた。通常であれば、誰もがその車を選ぶように設計されている。
被験者は2つのグループに分けられた。一方には十分に考える時間を与え、もう一方にはパズルをさせることで、意図的に熟考の時間を奪った。
まず、簡単な説明のみを加えた状態で選ばせたところ、どちらのグループもお買い得な車を選んだ割合に大きな差はなかった。
次に、燃費やトランク容量といった複雑な情報を追加したうえで選ばせたところ、十分に考える時間を与えられたグループでは、お買い得な車を選んだ割合が25%以下に減少した。一方、考える時間を与えられなかったグループでは、約60%がその車を正しく選択した。
考える時間が多すぎると、かえって判断が鈍ることがある。限られた時間内で直感的に選んだ方が、結果的に重要な情報に集中でき、より正確な判断ができるのだ。
選択肢を絞る
選択肢が多すぎると、人は「決めない」という選択に逃げる傾向がある。
この現象を証明する代表的な実験が、コロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガーによる、ジャムの試食販売実験である。
6種類のジャムを用意したケースでは、立ち寄った客は全体の40%だったが、実際に購入に至った割合は高かった。
一方、24種類のジャムを用意したケースでは、試食する客は60%と増加したものの、購入に至った割合はむしろ低下した。
選択肢が多すぎることで、かえって「買わない」という決断に至ってしまったのだろう。
こうした事態を避けるには、選択肢を絞ることが有効である。















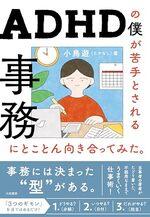

![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)