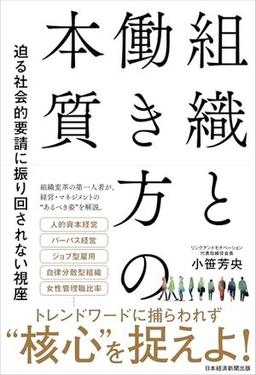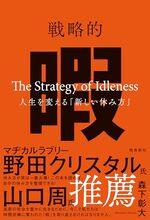会社と組織の本質
会社は人間の欲望をかなえるためにある
会社を英語でいうと、「カンパニー(Company)」となる。その語源はラテン語の「com(共に)」と「panis(パン)」に仲間を表す「-y」がついたもので、「一緒にパンを食べる仲間」という意味になる。この言葉は、会社という言葉が本来持っている共同体的なニュアンスをよく表している。
共同体的性格が変わり始めたのが、イギリスやオランダ、フランスなどの西欧諸国が、アジア諸国と貿易を行うために「東インド会社」を設立した1600年前後のことだ。
同社は「株式会社」という形態をとったことから、投資のリターンを求める株主だけではなく、アジアからの輸入品を売って儲けたい人、それらを買いたい人、働いて給料をもらいたい人などの欲望が、会社を通じて実現できるようになった。
そうやって生まれた会社は、それぞれの欲望を実現する「経済合理性」を中心軸として動く。つまり、儲からないことはやらないのだ。一方、社会には家族愛や友人愛、奉仕の精神といった多様な価値観が混在しており、経済合理性だけで動くわけではない。
結果、会社は摩擦やトラブルを引き起こす。別の言葉でいえば、会社は不祥事を起こす宿命を負っている。このことを私たちはしっかり理解しておく必要がある。
組織を成立させる3つの条件

組織と集団の違いは何か。電車の駅のホームに並ぶ人々でいうと、電車を待っている人は「集団」であるが、誰かがホームから線路に落ちてしまい、その人を救おうとする人たちは、その瞬間「組織」になる。つまり、人が集まっているだけなら「集団」だが、ある要件を満たしたら「組織」になるのだ。その要件とは、「共通の目的」「協働意志」「コミュニケーション」の3つである。
電車を待っている人たちは、電車で移動するという同じ目的はあるが、一緒に何かをやる協働意志やコミュニケーションはない。一方、ホームから落ちた人を救おうとする人たちには、救助という共通の目的や協働意志があり、そのためのコミュニケーションが自然に発生する。
組織は一時的なものであるため、存続するには「組織成果」と「個人の欲求充足」の2つが存続要件となる。そのために必要なのが「One for All, All for One(個人は組織のために、組織は個人のために)」の実現だ。
組織の問題は「人」ではなく、「間」にあると捉えるべきだ。個と個、チームとチーム、階層と階層、機能と機能などの「間」である。
組織の人数が増えれば「間」の数も増えるため、組織をうまく分化させて複雑性を縮減していく必要がある。
「人的資本経営」の真相
事業成果と人的資本の関係を紡ぐ
これまで、財務などの有形資産に関して情報開示が義務化されていたが、無形資産については義務化されていなかった。しかし、人材こそが企業の競争力の源泉であり、企業が成長発展するための重要な資本であることから、企業は投資家から無形資産のひとつ、人的資本に関する情報開示が求められるようになった。
この場合、経営戦略と人事戦略の連動が重要になる。それが意識されることなく、オリジナルの指標や施策を考えて発表しても、投資家から興味を持ってもらえなければ意味がない。実際、財務情報と非財務情報を掲載した「統合報告書」の発行にあたり、頭をひねって人的資本情報に関する独自の指標や施策を考え出している企業が多い。それらは企業価値の向上とは相関がなく、単なる自己満足に終わっているケースもある。人的資本情報の開示という手段が目的化しているのである。