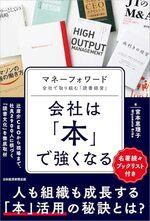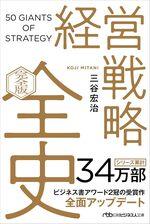【必読ポイント!】 生産性が上がっても実質賃金が上がらない理由
収奪的経済システムへの転落

継続的な成長率の向上には潜在成長率の引き上げが必要だが、「需要の前倒し」である金融政策、「所得の前借り」である財政政策の効果は一時的である。したがって、「拡張財政や金融緩和の不足が長期停滞の原因ではない」と多くのエコノミストは考える。
人口減少の影響以外で、著者が考える日本の長期停滞の理由は、たとえば次の2つである。大企業が儲けを溜めこみ、賃上げや人的投資が長期にわたっておろそかとなっていること、そして、社会情勢と連動した家計のリスクに応じられる社会保障制度へのアップグレードを政府が怠っていることだ。
成長戦略よりも所得再分配が優先と考えるのは、生産性はこの四半世紀で30%の上昇率を見せているにもかかわらず、実質賃金はむしろ3%減少しているからである。最近の春闘での賃上げ幅も物価高には追いついていない。
生産性の上昇率について日本よりやや劣後にあるフランスやドイツでも、実質賃金は上がっている。これらの国では、資本収益率を上回る企業付加価値を労働者にも分配する、レント・シェアリングという慣行が根づいているからだ。
日本では実質賃金への反映がまったくなされておらず、「家計が収奪されている」のである。
2024年のノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン、サイモン・ジョンソンの論考はこの問題を解くヒントになる。アセモグルとロビンソンのベストセラー、『国家はなぜ衰退するのか』では、衰退する国家は一部のエリートが富を独占する収奪的な制度をもつとする。自由競争と技術革新が広く奨励されてきた包摂的な制度のもとにあったはずの米国でも、イノベーションの果実である富が一部の人に集中し、金権政治の温床となっている。日本も、そのような収奪的社会へと足を踏み入れているのではないだろうか。
守りの経営の恒常化
借入をしながら投資主体になるべき企業が、1998年以降一貫して、借金を返済しつづける貯蓄主体のままである。バブル期の過剰投資などによる債務を返済するために、事業会社はコストカットによってバランスシートの健全化を進めた。そうして財務基盤を強化するのは至極まっとうなことだが、設備投資や人材育成などの前向きな行動が抑制されたままでは、「家計の貯蓄を企業の投資で吸収すること」ができない。そうしてマクロ経済が縮小均衡に至ることを「合成の誤謬」という。
不良債権問題が終息してもなお、大企業は財政基盤の強化を進め、賃上げをはじめとする支出の抑制という筋肉質な施策を続けた。リーマンショックに端を発する金融危機では輸出も急激に減少し、一部では倒産リスクにも直面した。このときの経験により、利益剰余金を積み上げる動きを加速した。その後も日本は多くの金融危機に見舞われ、攻めの経営を志す経営者は引責辞任を余儀なくされた。

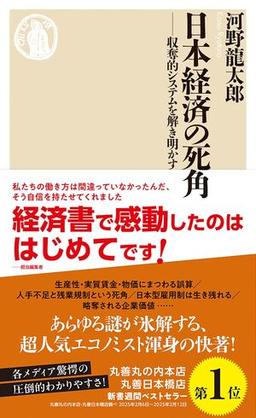





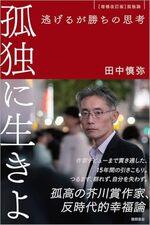

![大学教授のように小説を読む方法[増補新版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F4226_cover_150.jpg&w=3840&q=75)