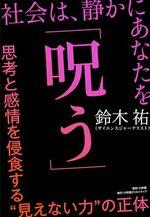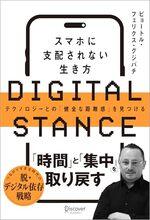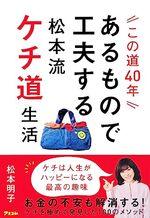西洋哲学と東洋思想
存在感を増す東洋思想

東洋思想は、現代の危機におおいに関わりを持つ。現代では、1つの危機が別の危機に組み込まれて、相関関係にある。したがって、単に複数の危機がある「複合危機」というよりも、「入れ子構造の危機」という言葉が当てはまる。この入れ子構造、ネットワークのネットワークにおいては、「安定した客体や点は関係の動きの結果にすぎず、客体は無限の関係が一時的に停止した点」でしかない。それが、現実そのものの形としての存在論だ。その点について、東洋思想が寄与してきた「すべてのものが相関している」という思想から、もっと精細に掘り下げなければならない。
インドで生まれた思想が2つに別れ、片方は西洋に行ってアフリカ(エジプト)の思想と融合、不変のものを探求する西洋哲学と一神教を生み出した。もう片方は東洋に行き、「変わらないものが存在するというのは幻想である、その幻想を克服しなければならない」とする東洋思想の源流となった。
西洋哲学と東洋思想には、どちらもパラドックスがある。東洋思想では、「すべてのものは変化しているが、変化は変わらない」としている。西洋哲学では、安定、永続したものを作ろうとしたが、たとえばギリシャの建築は何世紀も経るうちに廃墟になってしまった。
著者は、西洋と東洋が出会うグローバリゼーションの時代に育ち、東西双方の伝統から影響を受けてきたため、自身の描く存在論は、両者の統合を目指すものであるとしている。「21世紀はアジアの世紀」であり、「東洋思想がますます存在感を増す」だろう。
【必読ポイント!】 仏教との対話
日本には「実体」がある
ドイツの哲学者たちが日本に来ると、「ヘーゲルが『実体』と呼んだものがここにはまだある」と感じるという。ヘーゲルは、古代ギリシャ人には実体があり、デカルト以後の「近代人には主観、すなわち『自己』がある」と述べた。この実体とは、物には「目に見えない何か、共同体の形をつくる何かに関わる深い意味がある」こと、すなわち「物が意味のある形で結びついていること」を指す。
日本のビデオゲームを全部やりきったとしても、さらに新しいバージョンが考案されて、永遠に終わらない物語をプレイできる。そのように日本では何事においても、表面で何かを理解した気になっては、さらに別のレイヤーが現れて理解しきれなくなる、ということが起こる。「実体は変化でもありうるもの」であり、「むしろ変化が常態」だ。日本語には風を表現するさまざまな語彙があるように、「日本ではすべてが変化」するのである。