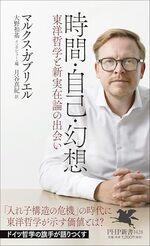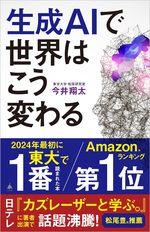そもそも私たちは「客観的」に世界を見ることができるのか
自分の見ている世界と隣の人が見ている世界は違う

「認知心理学」は、膨大な情報の中で人が何に注目し、どのように処理・理解し、知識を創り、意思決定をしているのかを問う学問だ。
私たちは何となく、「自分が見ている世界」と「隣の人が見ている世界」は同じだと思っているが、そうとは言いきれない。
数年前にSNSを中心に、1枚のドレスが写っている1枚の写真が流行った。それはある人には青と黒のボーダーのドレスに見えるのに、ある人には白と金のボーダーのドレスに見える。青と黒のボーダーに見える人が多いようだが、著者はそれを聞いてもなお白と金のドレスにしか見えない。
なぜこのような個人差があるのかは、実は明らかになっていない。おそらくは認知心理学の範囲である「知覚認知」の問題であるのだろう。
私たちがものを見る際には「かげ」の情報を無意識に使いながら、色を判断している。たとえば同じ黄色でも、光に当たった状態で見るのと、かげに置かれた状態で見るのとでは、見える色は異なる。網膜に実際に映っている色は違うのに、「かげ」の有無をふまえて無意識に「黄色だ」などと色を判断しているのだ。
「かげ」の情報を使っている自覚は見る人にはないため、先ほどのドレスは人によって違う色に見えるのではないかと考えられる。この仮説が今のところ有力ではあるが、まだ決定的とまではいえないようだ。
「見る」という認知過程ひとつとっても、万人に共通するものではない。ときには人によって見え方に違いがあるということだ。
人は「論理的思考」が苦手である
人間は「論理的な思考」が苦手だ。心理学の授業でほぼ必ず紹介されるある有名な実験は、それをよく表している。
イギリスのロンドン大学(当時)の心理学者ペーター・カスカート・ウェイソンが発表した、通称「ウェイソン課題」は、4枚のカードに関する問題を出した。
片面にアルファベットが書かれ、その裏側には数字が書いてあるカードがあり、「片面が母音ならその裏側は偶数でなければならない」という規則があるとする。この規則が守られているかを確かめるために、「E」「K」「4」「7」の4枚のカードのうち、どれを裏返す必要があるだろうか。