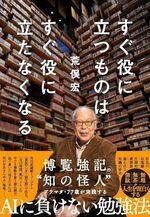幼少時代
門閥制度は、親の敵である
福澤諭吉は、豊前中津奥平藩の下級士族、福沢百助の末っ子として生まれた。父は大阪にある中津藩の倉屋敷で勤務していたが、諭吉が3歳のときに病死したため、母は兄弟を連れて中津に帰ることになった。
父は「銭を見るも汚れる」というような昔気質の純粋の学者であったので、役人の仕事に不平があったことだろう。だから、子どもたちは儒教主義で育てられ、厳格な父がいなくなった後も、「俗な卑しいことはしないものだ」と教えられていた。当時の時代状況では、父は自分で働き先を決めることができなかったのだろう。そのことが今でも気の毒である。
生前の父は、諭吉が成長したら寺に入れて坊主にするといつも言っていたそうだ。中津では先祖代々の身分制度があるが、身分の低い家に生まれた者でも、大僧正のような偉い坊様になった例はいくつもある。きっと父は、生まれつきの身分以上に息子を偉くしてあげようと思ったのだろう。45年の生涯で、父が封建制度に束縛されて何事もできず、不平を持ったままこの世を去ったのが残念でならない。門閥制度は、親の敵である。
お札を踏み、神社の神体を捨てる

12、13歳の頃、歩いていたところ紙を踏んでしまい、兄からひどく叱りつけられた。「殿様の名前が書かれている紙を踏むとはどういう心得だ」と言われて謝ったが、内心では「殿様の頭を踏んだわけでもないのに」とたいそう不満に思っていた。
殿様の名を書いた紙を踏んではいけないなら、神様のお名前のあるお札を踏んだらどうなるだろうと、人の見ていないところで踏んでみた。しかし、何も起こらない。